 :2025:05/18/18:29 ++ [PR]
:2025:05/18/18:29 ++ [PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
 :2009:05/18/13:49 ++ 政府に対するパブリックコメント
:2009:05/18/13:49 ++ 政府に対するパブリックコメント
パブリックコメント
2009/5/15
九州大学もったいない総合研究会 代表 久保 勇太
以下に、我々九州大学もったいない総合研究会の意見を述べさせていただきます。
(1) 我が国の温室効果排出ガスの中期目標(2020年)は、どの程度の排出量とすべきか(中期目標の6つの選択肢)
(意見)
我々は、② 2005 年比-6~-12%、1990 年比+1~-5%にするべきであると考えております。その理由については、
Ⅰ.他国の排出量との比較
Ⅱ.経済への影響
の項目ごとに述べさせていただきます。
Ⅰ.他国の排出量との比較
2005年度における日本のCO2排出量はおよそ13億トンですが、現在ではインドがその排出量を上回り、世界の中ではアメリカ、中国、ロシア、インドに次いで日本は第5位のCO2排出国となっております。
我が国は、先の2度に渡るオイルショックという危機を乗り越え、高効率の設備と省エネ技術で世界をリードして参りましたが、逆に、これ以上のCO2削減となると、これに伴う多大な試練が待ち受けていることは明らかです。
しかしながら、相対的な割合は低下してきているものの、依然として世界の中でも高い割合を占めており、高い環境技術、省エネ技術を誇る我が国は、これらの国々の中でも強いリーダーシップを発揮してCO2排出量削減に取り組んでいくべきだと思います。
Ⅱ.経済への影響
*この項目の具体的なシステム方式については、現在検討中です。
我々九州大学もったいない総合研究会は、経済をその原理に立ち返り、『物質の生産・流通・交換・分配とその消費・蓄積の全過程、およびその中で営まれる社会的関係の総体』であると捉え、現行の管理通貨制度に代わる全く新しい経済システムを導入することにより、経済への影響を最小になるように努力しつつ、CO2排出量削減に取り組んでいく、といった消極的な姿勢ではなく、むしろこの新しい枠組みにおける経済原理を駆使して野心的な目標のもとに、世界に先駆ける低炭素国家・持続可能型社会の構築を達成できるようなモデルを考案中です。
かいつまんで説明いたしますと、例えば新エネルギー技術に対して、リスクが大きいから投資を渋るのではなく、今後100年間のスパンで考えた場合、サステナブルの度合い(サステナジー指数)が大きくなるかどうかを評価し、それが圧倒的に大きくなれば、炭素市場においてその技術は高く評価され、それに対して投資が殺到するような枠組みと体制をせめて国内だけにおいても構築する必要性があると思います。
ただ、現状からそのような市場にただちに移行できるか、といわれると必ずしもそうではないので、低炭素革命を実施していくに当たり、経済に及ぶ影響を最小限に食い止めなければなりません。
我々が② 2005 年比-6~-12%、1990 年比+1~-5%にするべきである、とした理由はここにあります。目下の世界同時不況による日本の経済的損失は、バブル崩壊のそれ以上である、と我々は踏んでおります。従って不景気になれば、それに伴って自然にGDPが縮小するので、CO2排出量削減量も削減され、この影響で経産省が算出しております日本のGDPのピークアウトは2020年前半代に前倒しになると同時に、CO2排出量もピークアウトになると思います。
したがって、今回の不況を脱却する足掛かりとしての日本版・グリーンニューディールを野心的に実施していくべきであると思います。
(2) その中期目標の実現に向けて、どのような政策を実施すべきか
簡単ではありますが、以下に我々が検討している一部の政策案を提示いたします。
① 再生可能エネルギーへの巨額的な融資
世界同時不況の現状を鑑みる限り、20世紀で台頭したあらゆる産業は、一部の成長産業を除いて現状維持か、あるは斜陽産業となっていくことは間違いないでしょう。資源なき技術立国日本が生き残るためには、イノベーションをおいて他にございません。
2050年には国内の電力需要・供給構造も変えなければなりませんが、何よりも再生可能エネルギー市場への巨額の投資を引き出す必要性があります。これの旗手はまさに政府が担うべきであると思います。
・地熱発電(高温岩帯発電)を2020年までに商用発電を開始させるために、費用対効果を計上しない巨額の投資を行う。目標出力は300億KW/年以上とする。
・同時に風力プラントの国内開発を加速させ、日本の国土に応じた、風レンズを用いた小型の風力プラントなどを増設させていくあらゆる政策を展開する。
建築物の屋上に設置するなどの普及政策を徹底的に施行する。
・中小規模の水力発電の開発を促進させ、ローカル電源のベースとする。
・太陽光発電を新築住宅、オフィスビル、公共施設に対して設置の義務付け、それに伴う税制的な優遇措置を講じる。
全体で2020年までに国内電力供給における再生可能エネルギー(水力を含む)の割合を12~15%までに引き上げる必要性があると思います。
② 原子力発電の稼働率向上、リプレイスの促進
・原子力の点検を第3者の業者に義務付ける代わりに、点検期間のスパンを24か月に延長し、稼働率を向上させる。
・老朽化した出力の小さい原発から順次リプレイスしていく。なお、新規立地は行わない。
全体で2020年までに国内電力供給における2020年までには、40%程度までに引き上げる必要性があると思います。
③ モーダルシフト
・ITSを一般国道に対し整備し、カーシェアリングシステムや、コンパクト・シティの導入を、政令市を中心に促進させる。
・企業に対してはゼロエミッション車やクリーンディーゼル車の購入を義務化し、一般顧客に対しては流通促進のために、減税措置等を講じる。
・電車やバス料金などの引き下げを行い、現行のガソリン車に対し、炭素税の導入を2020年度までに始める。
(3) その他、2020 年頃に向けた我が国の地球温暖化対策に関する意見
現状のCDMやエコポイントといった場当たり的な対応ではなく、2050年の60~80%削減といった国際条約に値する公約を達成するために、日本が世界に先がけて第二の産業革命に向けて挑戦を始めるべき時であると思います。それは何も、『低酸素革命』に限った事ではないように思います。19世紀が大英帝国をはじめとしたヨーロッパの時代であり、20世紀がアメリカの時代であったのならば、共生の世紀である21世紀は日本を核としたアジアの世紀とするべきであり、すでにその片鱗が見えつつあります。
この時代に求められる日本の役割は、『和』と『質実剛健』を旨としたこの国民が潜在的に有しているはずの、自然との『調和』の精神を取り戻し、経済原理や利権によるしがらみではなく、全世界で想定される今後の危機に対し、どのような指導的役割を果たし、この危機を克服するために何ができるのか、を国民規模で対話し、平和国家としての本当の礎を築くことであり、世界の模範国家となることであると思います。
2020年までになすべきことは、これらをいかに実践していくかの枠組み作りであり、どうような国家変革を行えばよいかということです。
昨今のあらゆる分野における世界的危機と閉塞感の打破には、改革なくしてはあり得ません。今後の長きにわたって我が国ならず世界の国々は失う痛みを伴いながら未来を切り開いていかなければならない時代を迎えます。問題は選択肢が、軟着陸するのか、それとも強行的な胴体着陸をしなければならないのか、の2択しかないということです。避けられないのならば、軟着陸する手法を、国民をあげて議論していかなければなりません。この音頭がとれるのは、政府をおいて他にありません。
『低炭素革命』は日本が世界に対して21世紀の世界はどうあるべきかを提示するための絶好の国家プロジェクトであり、目下の危機をチャンスに変えるためのこれとない機会です。
地球温暖化対策は、現在のみならず、将来の長きにわたる世界全体に関わる安全保障です。これに向き合い戦う中で、日本が世界に対して強いメッセージを放ち、引いてはアジアのリーダーとして、各途上国に対し持続可能な、平和的繁栄の信頼関係を築くことも可能であると信じております。
我々九州大学もったいない総合研究会も微力ながら、これの実現のため研究活動を邁進していく所存です。
- +TRACKBACK URL+




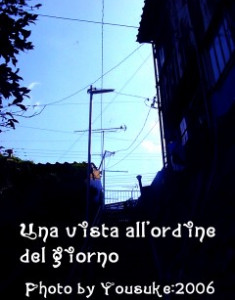
 :
: :0
:0 :
: 

