 :2025:05/18/07:36 ++ [PR]
:2025:05/18/07:36 ++ [PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
 :2009:05/08/01:34 ++ 二酸化炭素経済part1
:2009:05/08/01:34 ++ 二酸化炭素経済part1
二酸化炭素経済と共生型コミュニティ
もったいない総合研究会 総括班
『市民革命によって職業が自由化された⇒大量の物々交換の必要性⇒市場と金融の要請⇒資本主義社会・経済至上主義の台頭』
⇒富の分配機能(神の見えざる手)⇒不十分ではないか?
・資本主義は民主主義を運営していく上で、絶対的な役割を担ってきたという実績
⇒それ以外の体制の末路は近代200年間の歴史が物語っている。
⇒しかしながら、この期間は、人類の経済活動において、二酸化炭素という概念はほとんど付加されていなかった。
・二酸化炭素についての国際的な研究が具体的に開始されたのは、EUの主導により、1988年にIPCCが設立されてから
⇒二酸化炭素の“排出量”という言葉が用いられ始めたのはこれ以降
(『沈黙の春』レイチェル・カーソン(1968)やローマクラブの『成長の限界』(1972)においては、総体的な議論)
“二酸化炭素排出量”の概念は真新しいものであるのにも関わらず、経済活動に直接関連する重要なファクターである。
逆に言うと、経済活動がCO2によって支配されるという、新たな体制が確立される。
⇒もったいない総合研究会では、この体制を
『二酸化炭素経済』
と呼んでおり、これの台頭を非常に危惧している。
(理由)
・何も価値を見出されなかった“炭素”が、金と同等の価値を持つようになり、金本位制または管理通貨制度の崩壊を招く恐れがある。
・炭素を取引するために、資本が投資されるようになる。
・この炭素取引が経済の主体となり、“排出枠”を買い占めた国家・資本家が世界の覇権を握ることにより、ますます格差が増大する。
・取引の思惑により、自然環境に過大な負荷をかけ、当初の目的であった“低炭素社会=持続可能な社会(サステナジー)”とはかけ離れた方向に行く可能性を払底できない。
≪第一部のまとめ≫
『理念なき低炭素社会では、持続可能な社会を構築することはできない』
・人類が経済活動を行うと、二酸化炭素が排出されるのは自明の理
⇒これの回避は熱力学第二法則に反する。
・二酸化炭素の排出量を削減するには、どうすればよいのか?
◆“経済規模を縮小する”
⇒資本主義体制の崩壊を招きかねない。
(ただ、資本主義に代わる新たな体制が確立されれば、話は別である。また、金融による取引を必要としない経済システムが確立されても同じことが言える)
◆“(産業)人口を削減する“
⇒民主主義と相反する構想であり、最たる人権侵害であるが、日本をはじめ諸先進国では既に自然にこのような兆候が顕在化してきている。
(ある程度認識しなければならない真実である)
◆“新たなシステムを構築して、その中で二酸化炭素の取引をする”
⇒代表的なものに、京都メカニズムなどが挙げられる。
(これは、氷山の一角ともいうべき対象であって、昨年秋以来の金融恐慌以来、投資がすべて“低炭素”の方向に向かって流れているのは明らかである。大変喜ばしいことではあるが、この結末が世界に同様な結末をもたらすのかは、あまり議論されることはない。“低炭素”のみが果たしてサステナジーな社会を構築してくれるのか?我々はこのような懐疑的な一面も持ち合わせた上で、十分にこの結末を吟味していかなければならない。(例)バイオ燃料を作るために、世界の穀物価格バランスを崩す⇒世界的な食糧不足に陥る危険性)
⇒“炭素取引”は現に実用化されており、実際、我が国はこのメカニズムをもちいて2012を達成しようとしている。
(炭素が高額で取引されている最たる象徴)
・われわれが経済性(この場合豊かさ)を鑑みず、ひたすらに低炭素社会を実現するために邁進したとする(たとえば2050年までに世界全体でCO2半減)
⇒客観的に、われわれが不可抗力によって排出する二酸化炭素は森林吸収減等と等しくなり、理想的な炭素循環は実現すると思われる。
⇒しかしながら、われわれが経済市場原理を手放すということは、資本主義を放棄(または脱却)することであり、これすなわち、(現状の)民主主義体制の崩壊を意味する⇒第二の市民革命(産業革命)に匹敵するものでなければならない。
⇒(現状の不完全な体制では)最終的に炭素を通過機軸として、持たざる者(発展途上国)が持つ者(先進国)によって(市場、経済が)支配されるといった、帝国主義の再来たる懸念も生じてくる。
実際の話、現在10億にも満たない我々が先進国が、かつて一方的に確立した経済原理を用いて資源欲しさに世界各地に武力を用いて進出し、大量の化石資源を消費し、経済を発展させ世界を支配した挙句、その弊害は70億に達そうとしている世界人類の頭上とその未来に平等に降り注いでいる。
これは、産業革命&市民革命以降の世界の歴史の要約である。
■STEPにおいて、経済性を評価することは果たして可能なのか?
>>可能である。
■どうするのか?
>>もったいない総合研究会としては、“行為・概念の数値化”を検討している。
■どういうことか?
>>サステナジーな社会に即した社会活動または知的生産活動を、評価の最上位として位置づけ、この概念をもとに、経済システムを再構築する。
(詳細は第3部)
■実現見込みがあるのか?
>>現段階では、かなり少ない。しかしながら、かつてこのようなコミュニティーは世界中で多く存在していた。
(例)日本の江戸時代
■大まかな方向性
>>かつてこの国が200年間もの長きに渡って戦争がなく、完全に閉じたシステム(鎖国)の中で経済活動を全うしてきたという歴史と、和という調和を尊ぶ質実剛健な精神を思い返し、自然界に存在しているような、最小のエネルギーで駆動し、最も効率のよいシステムである生態系そのものが持つ食物連鎖、水循環、炭素循環等を参考とし、そのような自然の中で知恵とテクノロジーをはぐくみ、その中で共存する、といった経済システムを確立すること。
⇒近代の実績から、日本にしか成さない技ではないか?
全世界に先駆け、完全な『サステナジー社会』を実現するために、変革を起こしていく。
◆(現在の)低炭素革命の目的は、炭素に値段をつけて、経済の取引の材料にすることであり、本気で将来実現すべき『サステナジー社会』構築に向けて投資がなされているものではない。
⇒歴史は、埋蔵資源完全枯渇といった最終局面に直面した時に、繰り返す。
⇒この悪しき連鎖を断ち切らなければならない。
≪第二部のまとめ≫
『変えなければならないのは、弱者と強者を生み出す経済システムそのものであり、考えないといけないことは、これからの地球家族の共生の在り方である。』
もったいない総合研究会の経済の位置づけ(第3部)
『サステナジー社会』を実現するための経済性評価方法として、“行為・概念の数値化”という手法を導入する。
“行為・概念の数値化”とは?
・日本国憲法第14条に抵触するであろう、『思想・表現の自由』を評価することである。サステナジー社会を目指すことを第一義とする。
⇒さまざまな物議を醸し出すであろう、危険な手法。
このリスクを低減するために、日本は一体、何を目指すのか?というテーゼの下、改憲を実現する必要性がある。
⇒あまりにも無謀である。
◆“行為・概念の数値化”の導入の前に、『サステナジー推進法』の名のもとに、国民全体に『国民証』(すべての国民サービスを享受するための電子モバイルID)を配布する。
国内において存在・流通しているすべての様々な財(動産・不動産問わず)に対して『サステナジー指数』と呼ばれる数値を適用し、その財に対して、-100~100のランク付け作業を国民総出で行う(国勢調査の要領)。
この結果算出されたサステナジー指数を国民一人一人が把握し、これにいくつかのランク幅を設け、そのカテゴリーにおいて、様々な優遇措置、あるいは罰則が科せられる制度を設ける。
(例)トップランナー方式の最新家電を購入すれば、サステナジー指数が100近くチャージされ、購入の際に、消費税等が免除される。逆に中古で電気効率の悪い旧式の製品を購入すれば、サステナジー指数は逆に30程度ディスチャージされ、それに伴い、高利率の炭素税が課せられる。
このように、国内のすべての財に対し、サステナジー指数を適用し、国民が『サステナジー社会』を実現したくなるような購買意欲を掻き立てる政策を様々な分野に渡って施行する。
・また、企業の評価指数としての利用価値も十分に見込めるので、積極的に導入していくべきである。
・このサステナジー指数が十分に浸透したら、“サービスのサステナジー化”を推進していく。
ここで注意すべきは、サービスにおけるサステナジー化は“低炭素”ではなく、各人における『満足度=快適度=充足度』等を評価し、これを“豊かさ指数”(-100~100++)に変換し、これの総量でそのサービスを正しく評価する。これもサステナジー指数同様、これにいくつかのランク幅を設け、そのカテゴリーにおいて、様々な優遇措置、あるいは罰則が科せられる制度を設ける。これは、先述した通り、サステナジーな社会に即した業務活動、社会活動または知的生産活動等を、評価の最上位として位置づけ、国民の社会的身分に関わらず、一律に評価するものである。よって、このような活動を行うことが、各人にとって、直接的な“収入”となる。
(例)ある学生が、授業を受ける為に講義室に入る際IDを翳し、(IDに接続された電子化された)ノートにきちんと板書し、退室する際にIDを再び翳すことによって、その授業に真面目に出席し、きちんと板書したことによって、指数がチャージされる。この逆を行った学生は、もちろん相当数がディスチャージされる(これがサステナジーかどうかにおいては、議論の余地があるが、少なくとも学生は何らかの手段を用いて指数を稼がなければならない)(これは、あくまで個人の主観で決定される要素なので、各人が、“何をもって豊かであるか”をIDにあらかじめ入力しておく必要性がある)。
なお、この制度を適用していく段階に応じて、貨幣の流通量を段階的に減らしていき、キャッシュ(現金)を用いて財の交換を行うのではなく、サステナジー指数および豊かさ指数を用いて財を購入する、といった概念を国民の間で浸透させていく。最終的に、現金で財を購入する際は、多額の手数料を徴収するようにして、現金の流通を国内において事実上禁止する(諸外国との為替相場では円は維持)。
⇒有史以来続いてきた貨幣経済からの脱却および真の人間主義に基づく民主主義社会の構築が狙い(資本主義からの脱却という意味ではなく、貨幣に代わる、新たな為替の概念の導入)。
『システムのために人間が働く』のではなく『人間のために、システムを働かせる』体制を構築する必要性がある。
【ここまでのまとめ+CO2の展望】
・CO2は削減するべきである。
・ただし、これに伴って新たな経済システムを確立しなければならないのではないか、と考える。
・日本においては、2050年までに、絶対量としてCO2半減を達成するべきである。余裕があれば、それ以上の削減も見込んで政策を実施していくべきである。
・世界では、2050年において550ppmの基準を維持できるレベルでCO2排出量を抑えていく。
・先進国は、削減量に貢献するのは当然であるが、途上国に対し、持続可能型社会(サステナジー社会)はこうあるべきだ、という手本を見せるポリシーを貫いていくべきであって、国際社会もまた、このような国に対し何らかの賞賛や優遇措置を講じるべきである。
〈共生型コミュニティ〉
先述した経済システムに加えて
・サステナジー社会に対する国民の正しい理解と共感
・サステナジー社会構築を(中央からの指示ではなく)自治体レベルで実践していこうとする世論形成
・サステナジー社会を達成することの喜びと誇りを実感すること
の3点が不可欠である。
・義務教育の段階で、『何のために生きるのか』といった、哲学・道徳的教育を徹底し、自己の生を見つめ、利己主義・個人主義の危険性を加味した上での、『サステナジー』の在り方を議論し、国民性としての『和』を作り上げる。
・地域住民の交流を活性化し、失われつつある共同体としての本来のあり方を取り戻す。
・金で人が動くのではなく、心で人が動く社会が、真の共生型コミュニティであると思う。
- +TRACKBACK URL+




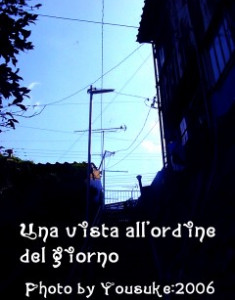
 :
: :0
:0 :
: 

