 :2025:05/18/03:20 ++ [PR]
:2025:05/18/03:20 ++ [PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
 :2009:05/07/23:38 ++ 地熱発電
:2009:05/07/23:38 ++ 地熱発電
火力発電・原子力発電などには、“廃熱”の問題がある。発電を行う際、その熱の三分の二は、水の沸騰に使われることもなく、そのまま放出されている。だが、地熱発電はその性質上発電の際無駄に放出されるエネルギーはほぼ皆無である。
地熱以外の火力、原子力発電所などの場合、沸騰させるための大量の水が必要だが、地熱発電の場合、その必要が無い。地熱発電では地熱貯留層(熱水溜まり、温泉の源のようなもの)を利用する。温泉を掘る要領でパイプを通してやると、地下から熱水が噴き上がり、地表に出たときには蒸気になっている。その蒸気を利用して、タービンを回している。
通常、地中は100m下がると、三度温度が上がると言われている。地熱発電は、地下2500m付近で行われるが、ここでは地下水の温度は約75度ある。ここでポイントになるのが地下に存在するマグマ溜まりである。さらに地下深く存在しているマグマの力によって、貯留層の温度は200度以上にもなる。地球の熱で温度上昇した水を、さらにマグマが加熱するのである。
アメリカの中西部にあるガイザーズという場所には、60万kwという大地熱発電所がある。この一帯に地熱発電所群があり、200万kw以上の出力を誇っている。地熱大国日本では、かなりの地熱での発電量のポテンシャルがあると期待される。
長所
・エネルギーを循環させている点(枯渇の心配がゼロ!)
この発電は、地下から“生産井”(地下に伸ばしている井戸)を通じて熱水を噴出させ、タービンを回すのに利用した後の蒸気を冷まして、再び“還元井”を通じて地中に埋めている。そのため、発電に利用した地熱貯留層では、熱水の減少や圧力の低下はほとんど無い。“生産井”から噴出した水蒸気を100%戻すことは無理だが、地中では雨水や地下水が貯留層に集まってくるので、減衰の心配は無い。
・新技術、『高温岩体発電』の可能性(38Gw以上)
これは、現在開発中の発電方法の一種で、まだ運用している場所は無いが、実用化間近ということで注目を浴びている。“地熱発電”は、地下2000m地点の、マグマ溜まりによって沸点まで熱せられた熱水を取り出すことによって発電している。
しかし、“高温岩体発電”はそのさらに深部、3000m近くまで井戸を掘ることによって、マグマ溜まりの存在が不要となる。地球のどの地点でも、地下3000mまでくると水が沸騰するぐらいの熱い岩盤だらけである。そして地上から水を勢いよく流し込み、岩盤に亀裂を入れて人工的な貯留層を作る。そのため、今まで貯留層を探すのに試験井を何本も掘って掛っていた無駄な時間とお金が必要無くなる。“高温岩体発電”は、3000m近くまで井戸を掘る、または深度2000m付近でも人口的に貯留層を作ることを言う。
この高温岩体発電では、設置場所を限定しないため、国内だけで38Gkw以上の発電が賄える資源量が存在すると言われている。
短所
・景観、熱水の枯渇を理由とした、観光業者などとの衝突
日本で地熱発電が積極的に推進されにくい理由は、地域住民の反対や法律上の規制があるためである。 つまり、候補地となりうる場所の多くが国立公園や国定公園に指定されていたり、温泉観光地となっていたりするため、景観を損なう発電所建設に理解を得にくいこと、温泉への影響に対する懸念があること、国立公園等の開発に関する規制があることなどである。 例えば、群馬県の嬬恋村では、現在地熱発電の計画が浮上しているが、その予定地が草津温泉の源泉から数kmしか離れていないため、温泉に影響が出る可能性があるとして草津町が反対している。
地熱発電によって温泉の湧出量が変化することはまず無い。その理由を以下に記す。
地熱発電は、その性質上開発から運転までのリードタイムが長く、多額の投資が必要な上に、開発リスクが大きいこと、さらに出力規模の問題もある。原発の平均は、1基で100万kw、火力の平均は50万kwだが、地熱の平均は5万kwしかない。だが、発電効率は現在8.3円/kwhにまで下がってきており、新エネルギーの中でも注目度は上がってきている。
1.時間がかかる
資源コストは限りなくゼロに近いが、発電に至るまでの準備時間がかかる。まず地熱貯留層を地上から見つけ、ボーリングをして評価をする。さらに実際に井戸を掘ってどれくらいの蒸気が出るのかを確認する作業にも時間がかかる。また折角貯留層を見つけても、規模が小さすぎたら採算が取れないリスクもある。
2.井戸に詰まるシリカスケールの除去
蒸気を噴き上げるための生産井と還元井はそれぞれ6~8本ほど設置されているが、地底から噴出する熱水に含まれる、シリカスケールというミネラルが溜まってパイプを詰まらせる。そのため5年に1本くらいの割合で新たに井戸を掘る必要があり、新しく井戸を掘るのに2000mの深度で約2億円はかかる。
だが、このシリカスケールからは、燃料電池に必要なリチウムや金など貴重な貴金属が非常に高濃度で濃集しているため、これを除去及び摘出し、有効活用しようという研究も行われている。
3.地熱に対するイメージ
地熱発電は、以前不正なお金の温床になりやすかった。最初に、地熱の貯留層探しのために試掘をするのだが、そこで有用な資源を掘り当てられるかどうかは誰にも分からない。結局試掘のために何年もかかって断念した、という報告書が提出されたとして、実際にはまともな調査を行わずに資金をもらっても誰も疑わない。この性質から、関係者に裏金が溜まりやすく、何十億もの不正金が存在していた。
そういったことがあり、いくら税金を注ぎこんでもまともな成果を上げられない発電だというレッテルが地熱に貼られてしまった。国がなかなか地熱に力を注がない理由の一つにこの事が挙げられている。
●高温岩体発電技術開発
昭和60~平成14年度,11年度事業費 2.2億円
高温であるが十分に天然の流体(熱水、蒸気)が含まれない岩盤を高温岩体(HDR:Hot Dry Rock)といい、火山国である日本には大量に賦存すると考えられています。高温岩体の持つ熱エネルギーを利用し発電するためには、まず地上から坑井を掘削し、高温の岩体に圧力を加えて人工的にき裂を造り、人工的な貯留層(き裂群)を造成します。次に地上から坑井(注入井)を使用して貯留層内に水を通過させ、岩体の熱エネルギーを奪った水を他の坑井(生産井)から蒸気・熱水として回収し、発電に利用します。
NEDOは、昭和55~61年度の7年間にわたり、IEAとの実施協定に基づき、日・米・西独3国による共同研究を米国ニューメキシコ州フェントンヒルにおいて行い、1ヵ月にわたり熱出力10MW級の循環抽熱試験に成功するなど、技術的経験・成果を蓄積しました。一方国内では昭和60年以来、山形県肘折において実験を行っています。
平成3年度には、深度1,800m(温度約250℃)付近の浅部人工貯留層に対して、約3ヵ月間の循環抽熱試験を行い、熱水・蒸気の安定回収に成功しました。また、深度2,200m(温度270℃)付近の深部人工貯留層に対して、平成7年度は25日間の予備循環抽熱試験を、平成8年度には1ヵ月間の導通改善循環試験を行い、熱水・蒸気の安定回収に成功しました。
平成11年度は、今後計画している2年間の長期循環試験のために必要な地上設備の設計、製作、工事等を平成10年度に引き続いて行いました。
かなり説明が不十分だと思いますが、政府も地熱発電を支援する対象としての『新エネルギー』に認めており、充分日本が主力の電力として進めていくべき一つに入っていると思います。アメリカ・フィリピンに次ぎ日本は世界第三位の発電容量を誇っています。火山大国日本として、地熱発電をもっと主張していくべきだと思います。
- +TRACKBACK URL+




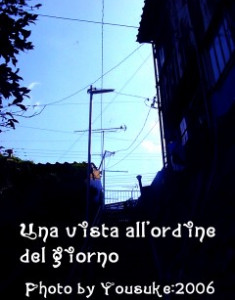
 :
: :0
:0 :
: 

