 :2025:05/18/08:10 ++ [PR]
:2025:05/18/08:10 ++ [PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
 :2009:05/08/01:36 ++ 二酸化炭素part1
:2009:05/08/01:36 ++ 二酸化炭素part1
もったいない総合研究会の経済の位置づけ(第一部)
≪経済≫
⇒『物質の生産・流通・交換・分配とその消費・蓄積の全過程、およびその中で営まれる社会的関係の総体』
資本主義体制にとって不可欠の要素
(裏返すと、資本主義体制でなければ不要)
≪資本≫
⇒経済というシステムに注入することにより、市場を駆動し、このシステムを制御する要素
⇒資本家が成長産業にたいして多額の投資を行い、イノベーションを実現
この結果、利潤が最大化される部分で、世界的な流通・交換・分配が行われ、そのストックとして、われわれが消費・蓄積を行う。
(現状は富の偏在)(例)先進国と途上国
<背景>
・経済が学問として台頭するようになった代表的名著にアダム=スミスの『国富論』(1776年)がある。
・同じ年に、アメリカが独立宣言を発表。
・欧米各地で市民革命の咆哮が上がる。
絶対王制の崩壊⇒近代市民社会=資本主義社会へ移行
(例)イギリスなどは市民革命を成し遂げつつ、産業革命に突入
『市民革命によって職業が自由化された⇒大量の物々交換の必要性⇒市場と金融の要請⇒資本主義社会・経済至上主義の台頭』
⇒富の分配機能(神の見えざる手)⇒不十分ではないか?
・資本主義は民主主義を運営していく上で、絶対的な役割を担ってきたという実績
⇒それ以外の体制の末路は近代200年間の歴史が物語っている。
⇒しかしながら、この期間は、人類の経済活動において、二酸化炭素という概念はほとんど付加されていなかった。
・二酸化炭素についての国際的な研究が具体的に開始されたのは、EUの主導により、1988年にIPCCが設立されてから
⇒二酸化炭素の“排出量”という言葉が用いられ始めたのはこれ以降
(『沈黙の春』レイチェル・カーソン(1968)やローマクラブの『成長の限界』(1972)においては、総体的な議論)
“二酸化炭素排出量”の概念は真新しいものであるのにも関わらず、経済活動に直接関連する重要なファクターである。
逆に言うと、経済活動がCO2によって支配されるという、新たな体制が確立される。
⇒もったいない総合研究会では、この体制を
『二酸化炭素経済』
と呼んでおり、これの台頭を非常に危惧している。
(理由)
・何も価値を見出されなかった“炭素”が、金と同等の価値を持つようになり、金本位制または管理通貨制度の崩壊を招く恐れがある。
・炭素を取引するために、資本が投資されるようになる。
・この炭素取引が経済の主体となり、“排出枠”を買い占めた国家・資本家が世界の覇権を握ることにより、ますます格差が増大する。
・取引の思惑により、自然環境に過大な負荷をかけ、当初の目的であった“低炭素社会=持続可能な社会(サステナジー)”とはかけ離れた方向に行く可能性を払底できない。
≪第一部のまとめ≫
『理念なき低炭素社会では、持続可能な社会を構築することはできない』
≪経済≫
⇒『物質の生産・流通・交換・分配とその消費・蓄積の全過程、およびその中で営まれる社会的関係の総体』
資本主義体制にとって不可欠の要素
(裏返すと、資本主義体制でなければ不要)
≪資本≫
⇒経済というシステムに注入することにより、市場を駆動し、このシステムを制御する要素
⇒資本家が成長産業にたいして多額の投資を行い、イノベーションを実現
この結果、利潤が最大化される部分で、世界的な流通・交換・分配が行われ、そのストックとして、われわれが消費・蓄積を行う。
(現状は富の偏在)(例)先進国と途上国
<背景>
・経済が学問として台頭するようになった代表的名著にアダム=スミスの『国富論』(1776年)がある。
・同じ年に、アメリカが独立宣言を発表。
・欧米各地で市民革命の咆哮が上がる。
絶対王制の崩壊⇒近代市民社会=資本主義社会へ移行
(例)イギリスなどは市民革命を成し遂げつつ、産業革命に突入
『市民革命によって職業が自由化された⇒大量の物々交換の必要性⇒市場と金融の要請⇒資本主義社会・経済至上主義の台頭』
⇒富の分配機能(神の見えざる手)⇒不十分ではないか?
・資本主義は民主主義を運営していく上で、絶対的な役割を担ってきたという実績
⇒それ以外の体制の末路は近代200年間の歴史が物語っている。
⇒しかしながら、この期間は、人類の経済活動において、二酸化炭素という概念はほとんど付加されていなかった。
・二酸化炭素についての国際的な研究が具体的に開始されたのは、EUの主導により、1988年にIPCCが設立されてから
⇒二酸化炭素の“排出量”という言葉が用いられ始めたのはこれ以降
(『沈黙の春』レイチェル・カーソン(1968)やローマクラブの『成長の限界』(1972)においては、総体的な議論)
“二酸化炭素排出量”の概念は真新しいものであるのにも関わらず、経済活動に直接関連する重要なファクターである。
逆に言うと、経済活動がCO2によって支配されるという、新たな体制が確立される。
⇒もったいない総合研究会では、この体制を
『二酸化炭素経済』
と呼んでおり、これの台頭を非常に危惧している。
(理由)
・何も価値を見出されなかった“炭素”が、金と同等の価値を持つようになり、金本位制または管理通貨制度の崩壊を招く恐れがある。
・炭素を取引するために、資本が投資されるようになる。
・この炭素取引が経済の主体となり、“排出枠”を買い占めた国家・資本家が世界の覇権を握ることにより、ますます格差が増大する。
・取引の思惑により、自然環境に過大な負荷をかけ、当初の目的であった“低炭素社会=持続可能な社会(サステナジー)”とはかけ離れた方向に行く可能性を払底できない。
≪第一部のまとめ≫
『理念なき低炭素社会では、持続可能な社会を構築することはできない』
PR
- +TRACKBACK URL+




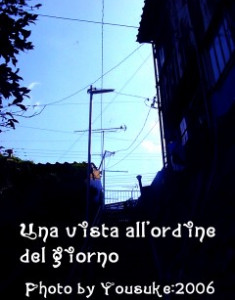
 :
: :0
:0 :
: 

