 :2025:05/18/12:33 ++ [PR]
:2025:05/18/12:33 ++ [PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
 :2009:10/08/10:21 ++ 炭素排出量取引について
:2009:10/08/10:21 ++ 炭素排出量取引について
排出量取引(はいしゅつりょうとりひき、英語:Emissions Trading, 略称:ET)とは、各国家や企業ごとに温室効果ガスの排出枠(キャップ)を定め、排出枠が余った国や企業と、排出枠を超えて排出してしまった国や企業との間で取引(トレード)する制度である。「排出権取引」、「排出枠取引」、「排出許可証取引」、「排出証取引」。京都議定書の第17条に規定されており、温室効果ガスの削減を補完する京都メカニズム(柔軟性措置)の1つ。
炭素クレジットは4種類あり、各国が持つ排出枠に対する削減量である初期割当量(Assigned Amount Unit, AAU)、各国が吸収源活動で得た吸収量(Removal Unit, RMU)、クリーン開発メカニズム事業で得られた認証排出削減量(Certified Emission Reductions, CER)、共同実施事業によって得られた排出削減ユニット(Emission Reduction Units, ERU)に分けられる。
カーボンオフセットなどに使われている、認証排出削減量(Certified Emission Reductions, CER)は、京都議定書で規定された、途上国への地球温暖化対策のための技術・資金援助スキームであるクリーン開発メカニズム(CDM)のルールに則って温室効果ガスを削減し、その排出削減量に基づき発行される国連認証のクレジットのこと。認証は第三者の認証機関が行うことになる。
附属書I締約国やその国内企業などは排出枠の配分を受ける。炭素クレジットを加味した最終的な排出量が配分された排出枠を下回っている(あるいは下回る見込みの)国や企業と、炭素クレジットを加味した最終的な排出量が配分された排出枠を上回っている(あるいは上回る見込みの)国や企業との間で、排出枠を売買することができる。
この考え方は国内(域内)排出量取引としても活用されている。EU 域内ではデンマークやイギリス、ドイツなどが国内排出量取引制度を設けているが、2005年 1月に EU 域内で共通の取引市場として機能する EU ETS(The EU Emissions Trading Scheme)が創設された。
排出量取引制度が導入された背景には、温室効果ガスの排出量を一定量削減するための費用が、国や産業種別によって違いがあることが挙げられる。例えば、未発達の技術を用いて経済活動をしている開発途上国では、すでに先進国で使われている技術を導入すれば温室効果ガスを削減できるので比較的小さい費用で済む。一方で、これまでに環境負荷を低減するために努力してきた先進国では、さらに温室効果ガスを削減するためには新しい技術やシステムを実用化する必要があり、多大な投資や労力が必要となる。
排出量取引の制度を導入すると、削減しやすい国や企業は炭素クレジットを売ることで利益を得られるので、削減に対するインセンティブが生まれ、より努力して削減しようとする。このように市場原理を生かして環境負荷を低減する手法を経済的手法という。これによって、社会全体としての削減費用が最も少ない形で温室効果ガスを削減することができると期待されている。
 :2009:10/08/08:22 ++ 資源・エネルギー庁
:2009:10/08/08:22 ++ 資源・エネルギー庁
資源エネルギー庁メールマガジン
経済産業省資源エネルギー庁
Agency for Natural Resources and Energy
URL http://www.enecho.meti.go.jp/
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
第45号 平成21年10月7日(水)発行
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
目次
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
◆巻頭メッセージ
◇トピック(1)
「太陽光発電買取制度室」の設置について
◆トピック(2)
「放射性廃棄物処分 広報強化月間」について
◇トピック(3)
第1回カナダCCSミッションの結果概要について
◆トピック(4)
「わかりやすい「エネルギー白書」の解説」について
◇イベント情報(1)
“放射性廃棄物地層処分に関する説明会 ~全国エネキャラバンin埼玉
考えよう!ニッポンのエネルギーのこと~”開催について
◆イベント情報(2)
科学体験ひろば~めざせ!エネルギー博士~開催について
◇イベント情報(3)
「グリーン・クリスマス・ライトアップ」参加施設の募集
◆イベント情報(4)
「グリーンエネルギークリエイティブコンテスト」
~一緒に描こう、みんなの未来~ 作品募集中!
◇イベント情報(5)
平成21年度 省エネコンテスト 参加者募集中!
~省エネはみんなで作る地球へのプレゼント~
◆新着情報・報道発表等
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
巻頭メッセージ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
「資源エネルギー庁メールマガジン」をお読みいただきありがとう
ございます。
○ 平成21年11月1日から「太陽光発電の新たな買取制度」が開始
されます。この制度の円滑な実施を目指し、経済産業省資源エネルギー庁
省エネルギー・審エネルギー部新エネルギー対策課に、「太陽光発電
買取制度室」が設置されました。詳しくは、「トピック(1)」を
ご覧ください。
○ 経済産業省では、放射性廃棄物の地層処分に関する国民全般の相互
理解を得るための活動の一環として、原子力の日(10月26日)を
含む10月の1か月間を「放射性廃棄物処分 広報強化月間」とし、
シンポジウムの開催などを行います。詳しくは、「トピック(2)」
をご覧ください。
○ 我が国から官民によるCCSミッションがカナダを訪問し、CCS
に関する日加協力について意見交換を実施しました。詳しくは、
「トピック(3)」をご覧ください。
○ 「エネルギー白書2009」のハイライトについてわかりやすく
ご紹介する「わかりやすい「エネルギー白書」の解説」は、「解説6:
中長期目標の設定に向けた国際交渉」まで掲載され、完結いたしました。
詳しくは、「トピック(4)」をご覧ください
○ 「イベント情報(1)」では、10月13日にさいたま市で開催
される放射性廃棄物地層処分に関する説明会「全国エネキャラバン
in 埼玉 考えよう!ニッポンのエネルギーのこと」についてご案内
しています。
○ 「イベント情報(2)」では、10月22日から25日まで北九州市
で開催される、楽しみながらエネルギーについて学べるイベント
“科学体験ひろば~めざせ!エネルギー博士”についてご案内しています。
○ 「イベント情報(3)」では、グリーン電力証書を活用し、全国の
ランドマーク施設等のイルミネーションで使用する電力をグリーン
エネルギーにすることを広く呼びかける「グリーン・クリスマス・
ライトアップ」参加施設の募集についてご案内しています。
○ グリーンエネルギーをわかりやすく、親しみやすく表現することを
テーマとしたポスター、動画を募集しています。
詳しくは、「イベント情報(4)」をご覧ください。
○ 現在、家庭や学校での優れた省エネルギーの取り組みを表彰する
「省エネコンテスト」の応募を受け付けています。
詳しくは、「イベント情報(5)」をご覧ください。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
トピック(1)
「太陽光発電買取制度室」の設置について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
経済産業省資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー対策課に、平成21年10月1日付けで、
「太陽光発電買取制度室」を設置し、平成21年11月1日から開始
される「太陽光発電の新たな買取制度」についての窓口機能を強化して、
円滑な制度実施を目指します。
(プレスリリース) http://www.meti.go.jp/press/20091001006/20091001006.html
太陽光発電の新たな買取制度につきましては、全国10カ所での説明会
「ソーラータウンミーティング」を実施中です。
制度の詳細につきましては、「買取制度ポータルサイト」をご参照ください。
(買取制度ポータルサイト) http://www.enecho.meti.go.jp/kaitori/index.html
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
トピック(2)
「放射性廃棄物処分 広報強化月間」について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
経済産業省では、放射性廃棄物の地層処分に関する国民全般の相互
理解を得るための活動の一環として、全都道府県説明会やワークショップ
等の活動を展開しています。
今般、原子力の日(10月26日)を含む10月の1か月間を
「放射性廃棄物処分 広報強化月間」とし、地層処分先進国のスウェーデン
から自治体等の要人を招聘したシンポジウムを開催するとともに、
経済産業省本省及び各地方経済産業局において懸垂幕や電光掲示板に
よる標語の掲載等を実施します。
また、処分事業の実施主体である原子力発電環境整備機構(NUMO
(ニューモ))においても理解促進に向けたキャンペーンを実施する
予定です。
詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
http://www.meti.go.jp/press/20091001002/20091001002.html
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
トピック(3)
第1回カナダCCSミッションの結果概要について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
9月21日から25日にかけて、我が国から官民によるCCS
ミッションがカナダを訪問しました。本ミッションでは、カナダ天然
資源省、アルバータ州政府、カナダ石炭協会などを訪問し、CCSに
関する日加協力について、意見交換を実施しました。
経済産業省としては、石炭火力発電のゼロエミッション化を実現
するため、今後も海外とのCCS協力に努めていく所存です。
http://www.meti.go.jp/press/20091001007/20091001007.html
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
トピック(4)
「わかりやすい「エネルギー白書」の解説」について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
昨今のエネルギーを取り巻く情勢について、説明やデータが盛り込まれ
ている「エネルギー白書2009」は本年5月に閣議決定され、9月9日
に発行されました。
そのハイライトについてわかりやすくご紹介する「わかりやすい
「エネルギー白書」の解説」については本メルマガ前号でもご紹介して
いましたが、「解説6:中長期目標の設定に向けた国際交渉」まで掲載
され、完結いたしました。
エネルギー白書(概要版・本文・わかりやすい「エネルギー白書」の
解説)へのリンクはこちら。
http://www.enecho.meti.go.jp/topics/hakusho/2009kaisetu/index_09.htm
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
イベント情報(1)
“放射性廃棄物地層処分に関する説明会 ~全国エネキャラバンin埼玉
考えよう!ニッポンのエネルギーのこと~”開催について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
放射性廃棄物の地層処分に関する国民全般の理解を得るための活動の
一環として、平成19年度から全都道府県単位で説明会を開催しています。
平成21年10月13日にさいたま市で開催いたしますので、ぜひご参加
ください。
記
1.日 時:平成21年10月13日(火)18:30~21:00
(終了予定)
2.場 所:さいたま市民会館おおみや(さいたま市大宮区下町3-47-8)
3.定 員:150名程度
4.参加費:無料
5.プログラム
<第一部>基調講演
テーマ:「46億歳の地球に、今、私たちができること」
生島 ヒロシ氏(フリーキャスター)
<第二部>ディスカッション
※ 参加は事前申し込みが必要です。申し込み方法など、詳しくは
放射性廃棄物ホームページ(http://www.enecho.meti.go.jp/rw/)を
ご覧ください。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
イベント情報(2)
科学体験ひろば~めざせ!エネルギー博士~開催について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
実際に展示物に見たり触れたりしながら、科学の不思議に触れ、
楽しみながら、エネルギーや原子力の大切さについて学ぼう!!
主に小・中学生、高校生向けに、「実験ステージ」や「実験テーブル」、
「体験型展示物」などを使い、楽しみながらエネルギーについて学べる
“科学体験ひろば~めざせ!エネルギー博士”を、10月22日(木)
~25日(日) に福岡県北九州市の西日本総合展示場(本館)にて
開催いたします。是非、ご家族でご参加下さい。
なお、詳細は当庁WEBまたは科学体験ひろば専用WEB
(http://www.ostec.or.jp/pop/en/hakase09/annai.htm)にてご確認
下さい。
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
イベント情報(3)
「グリーン・クリスマス・ライトアップ」参加施設の募集
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
経済産業省とグリーンエネルギー・パートナーシップは、「グリーン・
クリスマス・ライトアップ」事業に参加していただける施設を募集して
おります。
この事業はグリーン電力証書を活用し、全国のランドマーク施設や
大型商業施設等のイルミネーションで使用する電力をグリーンエネルギー
にすることを広く呼びかけるものです。
なお、応募締め切りは10月30日(金)となっております。
本事業に関する詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
http://www.green-energynet.jp/christmas_lightup/
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
イベント情報(4)
「グリーンエネルギークリエイティブコンテスト」
~一緒に描こう、みんなの未来~ 作品募集中!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
経済産業省とグリーンエネルギー・パートナーシップは、より多くの
人々にグリーンエネルギーを知っていただくために、「グリーンエネルギー
をわかりやすく、親しみやすく表現する」をテーマとしたポスター、動画を
募集します。
なお、応募締め切りは12月1日(火)となっております。
本事業に関する詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
http://www.green-energynet.jp/creative/
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
イベント情報(5)
平成21年度 省エネコンテスト 参加者募集中!
~省エネはみんなで作る地球へのプレゼント~
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
あなたが実践している省エネの知恵と工夫を教えてください。省エネに
取り組んでいる家庭や学校を募集します。だれもができそうなチョイエコ
な省エネから本格的に取り組んだ頑張る省エネまで、全国各地のみなさん
自慢の省エネ活動をふるってご応募ください。優秀作品には経済産業大臣賞
や資源エネルギー庁長官賞が授与されます。
参加申込みの締切りは11月13日、応募作品の送付は11月30日
締切りです。
応募方法等詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
http://www.enecho.meti.go.jp/contest/index.htm
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
新着情報・報道発表等
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
【プルサーマルシンポジウム in 高浜のアンケート結果について】
http://www.meti.go.jp/press/20091005002/20091005002.html
【エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業に係る家電の
販売状況について(9月7日~9月13日)】
http://www.meti.go.jp/press/20090916006/20090916006.html
【10月は3R(リデュース・リユース・リサイクル)推進月間】
http://www.meti.go.jp/press/20091002002/20091002002.html
【平成21年度「資源循環技術・システム表彰」の受賞者等の発表について】
http://www.meti.go.jp/press/20091002001/20091002001.html
【第2回グリーンITアワードの受賞結果について 】
http://www.meti.go.jp/press/20091005001/20091005001.html
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
【エネルギーの扉】(エネルギー関連リンク)
関連団体へのリンクのほか、「キッズページ」「エネルギー教育」など
コンテンツ別のリンクもあります!
http://www.enecho.meti.go.jp/others/links.htm
 :2009:10/04/14:20 ++ 開講案内
:2009:10/04/14:20 ++ 開講案内
Earth Environment and Energy
授業科目の領域: 社会性領域
単位数: 1単位
授業方法: 遠隔授業、1回2コマ×4回
開講学期及び
地区等: 後期 木曜4・5限(10/22,29, 11/5,12, 12/3(予備))
(主)箱崎理系地区21世紀交流プラザⅠ 1階多目的ホール(予備日は旧工学部本館4番講義室)
(副)伊都地区センター1号館1308教室
大橋地区5号館525号室
筑紫地区総合理工学府E棟1階101講義室
担当教員名(所属): 工藤 和彦 (高等教育開発推進センター)
TEL: 092-642-3926
E-mail: kudo@rche.kyushu-u.ac.jp
キーワード: 地球環境問題 エネルギー問題 資源
履修条件: なし
授業の目的: エネルギーと資源の大量消費によって地球温暖化問題や資源の減少、深刻な農業問題などがおこり、「エネルギー問題は地球と人類の将来を支配する問題」なのだという認識が定着してきた。
高度職業人(研究者を含む)となる大学院生諸君は、どの分野で仕事をすることになってもこのような地球規模の問題を意識して判断、行動することが要求される。また、一社会人の立場においても暮らしと地球規模の問題とをつねに結びつけて考えることも重要である。本講義では地球規模から産業、暮らしまでのエネルギー・環境問題の詳しい理解をめざす。
到達目標: •広範な地球環境問題を概観し、それぞれの重点を把握する。
•化石燃料、原子力、再生可能エネルギーなどさまざまなエネルギー資源の特性、現状と将来を
科学的に理解する。
•暮らしの中で現われるエネルギーと環境問題を考え、判断、行動する規範を考える。
授業の進め方: 講義資料を配布し、パワーポイントを用いて説明する。
授業計画: 講義回数: 4 回 ( 1回2コマ×4回)
1.地球環境問題の現状
2.エネルギーをめぐる世界情勢、エネルギー政策
3.化石燃料、原子力利用の現状と将来
4.再生可能エネルギー、代替エネルギーの展開
成績評価の方法: 授業中に討論を行い、また小論文の提出を求めて評価する。
教科書・参考書: 「エネルギーと環境」 佐藤正知他 三共出版 (2000)
「人間・環境・安全」 及川紀久雄他 共立出版 (2005)
学習相談: メール相談を原則として、必要に応じて予約により教員室で対応する。
 :2009:10/04/14:19 ++ 開講案内
:2009:10/04/14:19 ++ 開講案内
Management of Technology and Research / Basic
授業科目の領域: 社会性領域
(全学教育「研究と技術のマネジメント」との連携科目)
単位数: 2単位
授業方法: 遠隔授業
開講学期及び
地区等: 金曜3,4限( 2コマ×7回)10/9,16,23,30, 11/6,13,27 12/4(予備日)
箱崎地区旧工学部本館4番講義室(10/30のみ情報基盤研究センター多目的講習室)
伊都地区センター1号館1308号室
大橋地区5号館525号室
筑紫地区総理工E棟1階101講義室
担当教員名(所属): 谷川 徹 (産学連携センター/知的財産本部)
TEL: 092-642-4360
E-mail: tanigawa@astec.kyushu-u.ac.jp
キーワード: 市場、マネジメント、イノベーション、アントレプレナーシップ
履修条件: H20年度に同名科目のG2021を履修した者は、重複履修できない。
授業の目的: ビジネス界を含めた多様な経験と知識を持った講師陣が、最新の研究マネジメント、技術マネジメント等に関する講義を行って、大学における研究や学問の意義、目的、社会的位置づけ、方法等を再考するとともに、研究成果や技術の実用化、社会還元方法、ゴール設定のあり方等を、広い視野から学ぶ機会を提供する。今後の研究や学問への取り組み意欲の向上と目標設定、学び方の指針を与えることを目的とする。
講義はいわゆる技術マネジメント(MOT)の総合的かつ基礎的講義であり、大学内外で活躍する複数の講師が、毎回講義形式にて専門分野の知見を教授し、受講生とともに双方向のクラス運営を目指す。理系学生を主たる対象とするが、社会科学系、人文系の学生にとっても有用な内容である。
到達目標: 受講生に対して、大学の中では知り得ない広い視野、考え方に触れさせ、現在の研究や学問の位置づけや目標、進め方を問い直し、有効かつ効率的に学ぶ契機を与える。また今後の進路選択への有効な示唆を与える。また現在の激動するビジネス環境下、研究や技術をビジネスに生かす上での基本的知識、考え方のヒントを与える。
授業の進め方: 講師からの講義70~80%、質疑または討論30~20%の割合で構成し、可能な限り双方向のクラス運営を目指す。各回終了後レポートを課す。複数のキャンパスを結び遠隔授業を行う。
授業計画: 本講義は福岡銀行の寄附により開講される連携講義であり、下記要領による授業を計画している。講義回数は7回、180分/回
各回とも実業界経験講師を中心に講義とディスカッション形式の講義を行う予定。また適宜ゲストを招聘し、可能な限り双方向の授業を目指す(略歴と講義概要後述)。
10/9 研究構想論:研究構想策定と技術開発ロードマップ(安藤晴彦)
10/16 研究環境論:グローバル化とネット化時代の研究・技術マネジメント(山下勝比拡)
10/23 新事業創造論:新事業創出とアントレプレナーシップ(松本孝利)
10/30 事業戦略・知財マネジメント論:知財を事業戦略にどう生かすか(岡本清秀)
11/6 産学連携論:産学連携が国を変える、地域を変える、人を変える(谷川徹)
11/13 科学と社会論:研究の社会的意義、研究者のあり方、生き方とは(元村有希子)
********(11/20は休講) **************
11/27 ものづくり論:プロセスイノベーション神話からの脱却(大津留榮佐久)
(上記講義タイトル及び順序は暫定的であり、変更の可能性がある)
•各回90分の授業を、休憩を挟み2コマ連続して行う(計180分)。授業内容詳細は履修開始時までにシラバス・システムに掲示する。
•なお本講義は学部の高年次教養科目と共通して行う。
成績評価の方法: 出席50%、レポート(各回提出)内容30%、授業での積極性20%
教科書・参考書: 各講師が各授業において提示する
学習相談: 適宜受け付ける
【講師紹介/講義概要】
10月9日 ○安藤晴彦氏:内閣府参事官(科学技術政策・基本政策推進担当)
<経歴> 1985年通商産業省(現経済産業省)入省。スペイン大使館一等書記官、通商産業研究所(現経済産業研究所主任研究官、総括マネージャー、フェロー、資源エネルギー庁企画官(国際戦略・燃料電池担当)、燃料電池推進室長、新エネルギー対策課長、産業技術環境局 リサイクル推進課長等を歴任後現職。ノーベル賞(経済学)候補の青木昌彦スタンフォード大学名誉教授との共著、「モジュール化、新たな産業アーキテクチャーの本質」等でも著名な如く、産業アーキテクチャー、産業競争力分析研究等における論客としても著名。ベンチャー育成政策、科学技術政策、研究技術マネジメントにも明るい。電気通信大学特任教授。東京大学法学部卒。
<講義内容> 「研究構想論:研究構想策定と技術開発ロードマップ」
技術革新と産業アーキテクチャーが経済社会を大きく変革させる中、オープンイノベーションにみられるように、研究そのものの構想立案、実施手法も大きく変化しているが、モジュール化に代表される産業アーキテクチャーの変化について概説するとともに、技術ロードマップや技術マーケティング手法についても紹介する。今回は、地球温暖化というグローバルな問題へのソリューションとして期待のかかる、「クリーンテック」開発を例として講義を行う。
10月16日 ○山下勝比拡氏:(株)東芝理事(前(株)東芝産学連携グループ長)
<経歴> 1978年にImperial College, LondonでPh.D. 取得。翌年東芝入社。 システムエンジニア、設計部長、技術部長、技師長を経て、経営戦略部で事業戦略、事業開発も担当。現在、国内外の産学連携推進を担当。
日本オペレーションズリサーチ学会副会長&フェロー、トルコSabanci大学の国際アドバイザリーボードメンバー。東京工業大学、九州大学、青山学院大学の大学院客員教授、非常勤講師など歴任。国内外での産学連携に関する講演多数。
<講義内容> 「研究環境論:グローバル化とネット化時代の研究・技術マネジメント」
インターネットの普及などによる経済のグローバル化進展、途上国の急速な追い上げ、地球環境問題、資源枯渇問題等への対応など、事業環境の大きな変化のもとで日本は今後どのような進路をとるべきなのか、特に企業の経営、研究、開発における変革の必要性、企業と大学における人材育成の変革、社会や企業が求めるものの変化について、具体事例も含め、国際企業の第一線で研究や技術マネジメントを指揮してきた講師がインタラクティブな形式で講義を行う。
10月23日 ○松本孝利氏:アカデミーキャピタルインベストメンツ(株)代表取締役
(法政大学教授、元シスコシステムズ㈱代表取締役会長、元慶應義塾大学教授等)
<経歴> 1966年法政大学工学部電気工学科を卒業後、日本電子開発、日本DECを経て1984年独立し、人工知能の技術コンサルティングを行うベンチャーを設立。その後日本サン・マイクロシステムズを設立し社長に就任、また1992年には日本シスコシステムズを設立し社長に就任し、日本におけるインターネットの普及活動を展開、同社の日本における地位を不動にした。1995年以降米国Cisco Systems, Inc.日本担当副社長、同社アジア担当副社長、日本シスコシステムズ代表取締役会長を歴任し、2001年技術系ベンチャーへの投資にフォーカスしたアカデミー キャピタル インベストメンツ㈱を設立して社長に就任、現在に至る。投資活動のかたわら、大学における教育と大学発ベンチャー支援活動も積極的に行っている。
<講義内容> 「新事業創造論:新事業創出とアントレプレナーシップ」
ベンチャービジネスの先進国である米国でのベンチャービジネスが経済や社会に与えた意義を1980~2000年台のIT産業を例に考え、更に日本のそれと比較して検証する。 次に、教育・研究環境で生まれた知見や新しい技術をベースにしたベンチャーの必要性を考えると共に、起業において必要な要素であるアントレプレナーシップ、起業機会、ビジネスモデルの開発、経営戦略、などについての概要を説明する。また、講義の後半では実際にベンチャー経営に携わっている起業家をゲストとして招き、企業概要、ビジョン、ビジネスモデル、経営戦略、などをお話いただいた後、彼が起業に関わった経緯や理由、そして仕事や生き方についての考えをお話いただく。 最後に本講義に参加している学生たちと”ゲストを交えたディスカッション行う。
10月30日 ○岡本清秀氏:岡本IPマネジメント代表
(神戸大学客員教授、日本ライセンス協会前会長、日本知財学会理事、前オムロン㈱知財部長)
<経歴> 大阪市立大学工学部電気工学科卒業後、立石電機(株)(現オムロン(株))に入社。以後 制御本部を経て特許部へ異動。その後米国カリフォルニア研究開発子会社での特許業務統括、本社特許部での国内外知的財産関連業務担当など、同社の特許業務を一貫して担当、1997年に同社知的財産部長に就任し同社の知財総責任者として活躍した。2008年同社を退職し岡本IPマネジメントを設立、代表に就任し現在に至る。
<講義内容> 「事業戦略・知財マネジメント論:知財を事業戦略にどう生かすか」
世界の大きな環境変化により、技術イノベーションなくして日本の産業は生き残れない。日本の生き残りを支える技術、事業を戦略的に支援するのが知的財産である。本講では、次のテーマに沿って講義を行い、日本の産業のこれからの生き残りのための知財戦略と期待される技術者像について検討する。
(1)知的財産の基礎、(2)企業における知的財産の役割、(3)特許侵害訴訟事件、(4)職務発明事件などの事例解説、(5)戦後に日本の産業の発展、(6)日本の企業と大学を取り囲む世界の現状(アジアの台頭)、(7)日本の企業のこれからの知財戦略、(8)期待される技術者像について
11月6日 ○谷川徹:九州大学産学連携センター教授/副センター長、知的財産本部国際産学官連携センター長、
ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー長(元日本政策投資銀行、元スタンフォード大学客員研究員等)
<経歴> 日本開発銀行(現日本政策投資銀行)で27年間、企業審査、プロジェクトファイナンス等産業金融の他、業務企画、予算折衝、地域開発企画、対日投資コンサルティング、米国駐在他、多彩な業務の責任者として活動。2000年同行を辞した後渡米、スタンフォード大学客員研究員として、シリコンバレー型地域活性化手法の研究や米国の産学連携、ハイテクベンチャー育成策の研究を行った。また同地のベンチャー企業のアドバイザーとしても活動、産学連携手法、ベンチャー育成策、地域活性策の実践的研究を進めた。現在は広いネットワークを生かして九州大学国際産学官連携推進の責任者として活動中。専門は地域経済政策、ベンチャービジネス育成、産学連携。京都大学法学部卒。
<講義内容> 本講義は、産学連携を国際比較し、また日本における歴史的展開を俯瞰しつつ、産学連携が大学・研究機関と国・社会・産業界・地域双方に与える影響、今日的な課題について明らかにする。大学の研究・教育が国や地域のイノベーションに与える効果を説くとともに、研究者・技術者・学生にとっての意味・意義・方法を示して、産学連携に対する新たな取り組みの意欲を喚起する。具体的な産学連携を行っている研究者又は起業家をゲストとして迎え、受講者と議論を進める予定。
11月13日 ○元村有希子氏:毎日新聞科学環境部記者
<経歴> 毎日新聞入社後、地方支局、東京本社編成総センター等を経て科学環境部に配属。
2002年1月から2年数ヶ月、64回にわたり毎日新聞科学面に連載した「理系白書」により2006年に第一回科学ジャーナリスト大賞を受賞。科学と社会のあり方、高等教育のあり方等に関する講演や著作多数。九州大学教育学部卒。
<講義内容> 「科学と社会論:研究の社会的意義、研究者のあり方、生き方とは」
21世紀の科学者は、誰のために、どのような活動をするのか。重要なのは「社会のための科学」と言う視点であるが、科学と社会との間には思いのほか深くて広い溝がある。また日本では、子供たちが理科を嫌がり、理工系への進学を敬遠する傾向が強まっている。社会が科学者に対して、一面的なイメージを抱いていることも大きい。講義では、社会における科学・技術の位置づけをいくつかのデータから概観し、21世紀に求められる科学、研究者像について提案する。
11月27日 ○大津留榮佐久氏:(財)福岡県産業・科学技術振興財団システムLSI推進プロデューサー兼
福岡先端システムLSI開発クラスター戦略本部事業総括
(九州大学、九州工業大学、福岡大学、立命館アジア太平洋大学客員教授等)
<経歴> 米半導体大手 Texas Instrument Japanに約22年間在職、技術マーケティング、ファウンドリー開発等のマネージャー等歴任後、ソニーセミコンダクター九州(株)に転じ、実装部門 、国際資材調達部門等のトップとして活躍。九州大学工学研究院ユーザーサイエンス機構特任教授を経て、現在福岡県の進めるシリコンシーベルト構想の総指揮をとると共に、知的クラスター創成事業(第Ⅱ期)の事業総括を務める。IT業界を中心に技術マーケティングから研究開発マネジメント、生産マネジメントまでのバリューチェーン全般を、実践的なMOT体系にて、理工系大学や企業にて講義多数。福岡大学工学部電気工学科卒。
<講義内容> 「ものづくり論:プロセスイノベーション神話からの脱却」
オープンイノベーションが台頭し、各国内産業セクターにも波及し始めている。例えば大手資源・エネルギー開発企業においても「技術開発の最速化」と「ビジネスモデルの革新」がより推進されようとしている。そして技術開発の最前線においては、先端技術開発の先にある新たな基軸(技術の複合化・統合化)やサービス・用途の多様化(多様なコンテンツ、多様な用途)に連動する次世代マイルストーンが模索されている。日本企業が強みとしてきた「ものづくり論」を再評価しながら、グローバル市場に対峙できる「新たなものづくり論」をMOT視点で講述する。特に何を作るべきかよりも如何に作るべきか(プロセスイノベーション)に陥りがちな日本企業の限界を超える考え方を提案する。
 :2009:10/03/21:38 ++ HP利用にあたっての注意
:2009:10/03/21:38 ++ HP利用にあたっての注意
①GCM総合掲示板には、新旧HPに新たに投稿があったことを掲示する
②特に、新HPの各部門ごとに議論すべきトピックについては、その告知を問う掲示板にて行い、基本的に当掲示板では細かい議論は行わない
③旧HPは、もっ総研全体での活動の報告を掲示する。
④各部門で新たな動きがあった場合は、当掲示板にその旨を掲示し、部門のページにて詳細を報告する
⑤諸連絡は掲示板を通じて行うようにする。掲示板を見なかったことによって生じた不利益は自己責任とする




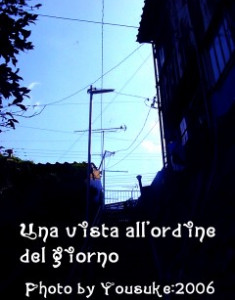
 :
: :0
:0 :
: 
