 :2025:05/18/02:51 ++ [PR]
:2025:05/18/02:51 ++ [PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
 :2009:10/08/10:21 ++ 炭素排出量取引について
:2009:10/08/10:21 ++ 炭素排出量取引について
排出量取引(はいしゅつりょうとりひき、英語:Emissions Trading, 略称:ET)とは、各国家や企業ごとに温室効果ガスの排出枠(キャップ)を定め、排出枠が余った国や企業と、排出枠を超えて排出してしまった国や企業との間で取引(トレード)する制度である。「排出権取引」、「排出枠取引」、「排出許可証取引」、「排出証取引」。京都議定書の第17条に規定されており、温室効果ガスの削減を補完する京都メカニズム(柔軟性措置)の1つ。
炭素クレジットは4種類あり、各国が持つ排出枠に対する削減量である初期割当量(Assigned Amount Unit, AAU)、各国が吸収源活動で得た吸収量(Removal Unit, RMU)、クリーン開発メカニズム事業で得られた認証排出削減量(Certified Emission Reductions, CER)、共同実施事業によって得られた排出削減ユニット(Emission Reduction Units, ERU)に分けられる。
カーボンオフセットなどに使われている、認証排出削減量(Certified Emission Reductions, CER)は、京都議定書で規定された、途上国への地球温暖化対策のための技術・資金援助スキームであるクリーン開発メカニズム(CDM)のルールに則って温室効果ガスを削減し、その排出削減量に基づき発行される国連認証のクレジットのこと。認証は第三者の認証機関が行うことになる。
附属書I締約国やその国内企業などは排出枠の配分を受ける。炭素クレジットを加味した最終的な排出量が配分された排出枠を下回っている(あるいは下回る見込みの)国や企業と、炭素クレジットを加味した最終的な排出量が配分された排出枠を上回っている(あるいは上回る見込みの)国や企業との間で、排出枠を売買することができる。
この考え方は国内(域内)排出量取引としても活用されている。EU 域内ではデンマークやイギリス、ドイツなどが国内排出量取引制度を設けているが、2005年 1月に EU 域内で共通の取引市場として機能する EU ETS(The EU Emissions Trading Scheme)が創設された。
排出量取引制度が導入された背景には、温室効果ガスの排出量を一定量削減するための費用が、国や産業種別によって違いがあることが挙げられる。例えば、未発達の技術を用いて経済活動をしている開発途上国では、すでに先進国で使われている技術を導入すれば温室効果ガスを削減できるので比較的小さい費用で済む。一方で、これまでに環境負荷を低減するために努力してきた先進国では、さらに温室効果ガスを削減するためには新しい技術やシステムを実用化する必要があり、多大な投資や労力が必要となる。
排出量取引の制度を導入すると、削減しやすい国や企業は炭素クレジットを売ることで利益を得られるので、削減に対するインセンティブが生まれ、より努力して削減しようとする。このように市場原理を生かして環境負荷を低減する手法を経済的手法という。これによって、社会全体としての削減費用が最も少ない形で温室効果ガスを削減することができると期待されている。
- +TRACKBACK URL+




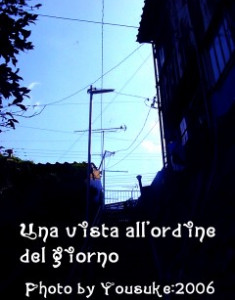
 :
: :0
:0 :
: 

