 :2025:05/18/05:01 ++ [PR]
:2025:05/18/05:01 ++ [PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
 :2009:05/14/11:03 ++ 二酸化炭素Part3
:2009:05/14/11:03 ++ 二酸化炭素Part3
もったいない総合研究会の経済の位置づけ(第3部)
『サステナジー社会』を実現するための経済性評価方法として、“行為・概念の数値化”という手法を導入する。
“行為・概念の数値化”
とは?
・日本国憲法第14条に抵触するであろう、『思想・表現の自由』を評価することである。サステナジー社会を目指すことを第一義とする。
⇒さまざまな物議を醸し出すであろう、危険な手法。
このリスクを低減するために、日本は一体、何を目指すのか?というテーゼの下、改憲を実現する必要性がある。
⇒あまりにも無謀である。
◆“行為・概念の数値化”の導入の前に、『サステナジー推進法』の名のもとに、国民全体に『国民証』(すべての国民サービスを享受するための電子モバイルID)を配布する。
国内において存在・流通しているすべての様々な財(動産・不動産問わず)に対して『サステナジー指数』と呼ばれる数値を適用し、その財に対して、-100~100のランク付け作業を国民総出で行う(国勢調査の要領)。
この結果算出されたサステナジー指数を国民一人一人が把握し、これにいくつかのランク幅を設け、そのカテゴリーにおいて、様々な優遇措置、あるいは罰則が科せられる制度を設ける。
(例)トップランナー方式の最新家電を購入すれば、サステナジー指数が100近くチャージされ、購入の際に、消費税等が免除される。逆に中古で電気効率の悪い旧式の製品を購入すれば、サステナジー指数は逆に30程度ディスチャージされ、それに伴い、高利率の炭素税が課せられる。
このように、国内のすべての財に対し、サステナジー指数を適用し、国民が『サステナジー社会』を実現したくなるような購買意欲を掻き立てる政策を様々な分野に渡って施行する。
・また、企業の評価指数としての利用価値も十分に見込めるので、積極的に導入していくべきである。
・このサステナジー指数が十分に浸透したら、“サービスのサステナジー化”を推進していく。
ここで注意すべきは、サービスにおけるサステナジー化は“低炭素”ではなく、各人における『満足度=快適度=充足度』等を評価し、これを“豊かさ指数”(-100~100++)に変換し、これの総量でそのサービスを正しく評価する。これもサステナジー指数同様、これにいくつかのランク幅を設け、そのカテゴリーにおいて、様々な優遇措置、あるいは罰則が科せられる制度を設ける。これは、先述した通り、サステナジーな社会に即した業務活動、社会活動または知的生産活動等を、評価の最上位として位置づけ、国民の社会的身分に関わらず、一律に評価するものである。よって、このような活動を行うことが、各人にとって、直接的な“収入”となる。
(例)ある学生が、授業を受ける為に講義室に入る際IDを翳し、(IDに接続された電子化された)ノートにきちんと板書し、退室する際にIDを再び翳すことによって、その授業に真面目に出席し、きちんと板書したことによって、指数がチャージされる。この逆を行った学生は、もちろん相当数がディスチャージされる(これがサステナジーかどうかにおいては、議論の余地があるが、少なくとも学生は何らかの手段を用いて指数を稼がなければならない)(これは、あくまで個人の主観で決定される要素なので、各人が、“何をもって豊かであるか”をIDにあらかじめ入力しておく必要性がある)。
なお、この制度を適用していく段階に応じて、貨幣の流通量を段階的に減らしていき、キャッシュ(現金)を用いて財の交換を行うのではなく、サステナジー指数および豊かさ指数を用いて財を購入する、といった概念を国民の間で浸透させていく。最終的に、現金で財を購入する際は、多額の手数料を徴収するようにして、現金の流通を国内において事実上禁止する(諸外国との為替相場では円は維持)。
⇒有史以来続いてきた貨幣経済からの脱却および真の人間主義に基づく民主主義社会の構築が狙い(資本主義からの脱却という意味ではなく、貨幣に代わる、新たな為替の概念の導入)。
(具体的な内容は第4部で述べる)
≪第3部のまとめ≫
『システムのために人間が働く』のではなく『人間のために、システムを働かせる』体制を構築する必要性がある。
もったいない総合研究会の経済の位置づけ(第3部)
『サステナジー社会』を実現するための経済性評価方法として、“行為・概念の数値化”という手法を導入する。
“行為・概念の数値化”
とは?
・日本国憲法第14条に抵触するであろう、『思想・表現の自由』を評価することである。サステナジー社会を目指すことを第一義とする。
⇒さまざまな物議を醸し出すであろう、危険な手法。
このリスクを低減するために、日本は一体、何を目指すのか?というテーゼの下、改憲を実現する必要性がある。
⇒あまりにも無謀である。
◆“行為・概念の数値化”の導入の前に、『サステナジー推進法』の名のもとに、国民全体に『国民証』(すべての国民サービスを享受するための電子モバイルID)を配布する。
国内において存在・流通しているすべての様々な財(動産・不動産問わず)に対して『サステナジー指数』と呼ばれる数値を適用し、その財に対して、-100~100のランク付け作業を国民総出で行う(国勢調査の要領)。
この結果算出されたサステナジー指数を国民一人一人が把握し、これにいくつかのランク幅を設け、そのカテゴリーにおいて、様々な優遇措置、あるいは罰則が科せられる制度を設ける。
(例)トップランナー方式の最新家電を購入すれば、サステナジー指数が100近くチャージされ、購入の際に、消費税等が免除される。逆に中古で電気効率の悪い旧式の製品を購入すれば、サステナジー指数は逆に30程度ディスチャージされ、それに伴い、高利率の炭素税が課せられる。
このように、国内のすべての財に対し、サステナジー指数を適用し、国民が『サステナジー社会』を実現したくなるような購買意欲を掻き立てる政策を様々な分野に渡って施行する。
・また、企業の評価指数としての利用価値も十分に見込めるので、積極的に導入していくべきである。
・このサステナジー指数が十分に浸透したら、“サービスのサステナジー化”を推進していく。
ここで注意すべきは、サービスにおけるサステナジー化は“低炭素”ではなく、各人における『満足度=快適度=充足度』等を評価し、これを“豊かさ指数”(-100~100++)に変換し、これの総量でそのサービスを正しく評価する。これもサステナジー指数同様、これにいくつかのランク幅を設け、そのカテゴリーにおいて、様々な優遇措置、あるいは罰則が科せられる制度を設ける。これは、先述した通り、サステナジーな社会に即した業務活動、社会活動または知的生産活動等を、評価の最上位として位置づけ、国民の社会的身分に関わらず、一律に評価するものである。よって、このような活動を行うことが、各人にとって、直接的な“収入”となる。
(例)ある学生が、授業を受ける為に講義室に入る際IDを翳し、(IDに接続された電子化された)ノートにきちんと板書し、退室する際にIDを再び翳すことによって、その授業に真面目に出席し、きちんと板書したことによって、指数がチャージされる。この逆を行った学生は、もちろん相当数がディスチャージされる(これがサステナジーかどうかにおいては、議論の余地があるが、少なくとも学生は何らかの手段を用いて指数を稼がなければならない)(これは、あくまで個人の主観で決定される要素なので、各人が、“何をもって豊かであるか”をIDにあらかじめ入力しておく必要性がある)。
なお、この制度を適用していく段階に応じて、貨幣の流通量を段階的に減らしていき、キャッシュ(現金)を用いて財の交換を行うのではなく、サステナジー指数および豊かさ指数を用いて財を購入する、といった概念を国民の間で浸透させていく。最終的に、現金で財を購入する際は、多額の手数料を徴収するようにして、現金の流通を国内において事実上禁止する(諸外国との為替相場では円は維持)。
⇒有史以来続いてきた貨幣経済からの脱却および真の人間主義に基づく民主主義社会の構築が狙い(資本主義からの脱却という意味ではなく、貨幣に代わる、新たな為替の概念の導入)。
(具体的な内容は第4部で述べる)
≪第3部のまとめ≫
『システムのために人間が働く』のではなく『人間のために、システムを働かせる』体制を構築する必要性がある。
『サステナジー社会』を実現するための経済性評価方法として、“行為・概念の数値化”という手法を導入する。
“行為・概念の数値化”
とは?
・日本国憲法第14条に抵触するであろう、『思想・表現の自由』を評価することである。サステナジー社会を目指すことを第一義とする。
⇒さまざまな物議を醸し出すであろう、危険な手法。
このリスクを低減するために、日本は一体、何を目指すのか?というテーゼの下、改憲を実現する必要性がある。
⇒あまりにも無謀である。
◆“行為・概念の数値化”の導入の前に、『サステナジー推進法』の名のもとに、国民全体に『国民証』(すべての国民サービスを享受するための電子モバイルID)を配布する。
国内において存在・流通しているすべての様々な財(動産・不動産問わず)に対して『サステナジー指数』と呼ばれる数値を適用し、その財に対して、-100~100のランク付け作業を国民総出で行う(国勢調査の要領)。
この結果算出されたサステナジー指数を国民一人一人が把握し、これにいくつかのランク幅を設け、そのカテゴリーにおいて、様々な優遇措置、あるいは罰則が科せられる制度を設ける。
(例)トップランナー方式の最新家電を購入すれば、サステナジー指数が100近くチャージされ、購入の際に、消費税等が免除される。逆に中古で電気効率の悪い旧式の製品を購入すれば、サステナジー指数は逆に30程度ディスチャージされ、それに伴い、高利率の炭素税が課せられる。
このように、国内のすべての財に対し、サステナジー指数を適用し、国民が『サステナジー社会』を実現したくなるような購買意欲を掻き立てる政策を様々な分野に渡って施行する。
・また、企業の評価指数としての利用価値も十分に見込めるので、積極的に導入していくべきである。
・このサステナジー指数が十分に浸透したら、“サービスのサステナジー化”を推進していく。
ここで注意すべきは、サービスにおけるサステナジー化は“低炭素”ではなく、各人における『満足度=快適度=充足度』等を評価し、これを“豊かさ指数”(-100~100++)に変換し、これの総量でそのサービスを正しく評価する。これもサステナジー指数同様、これにいくつかのランク幅を設け、そのカテゴリーにおいて、様々な優遇措置、あるいは罰則が科せられる制度を設ける。これは、先述した通り、サステナジーな社会に即した業務活動、社会活動または知的生産活動等を、評価の最上位として位置づけ、国民の社会的身分に関わらず、一律に評価するものである。よって、このような活動を行うことが、各人にとって、直接的な“収入”となる。
(例)ある学生が、授業を受ける為に講義室に入る際IDを翳し、(IDに接続された電子化された)ノートにきちんと板書し、退室する際にIDを再び翳すことによって、その授業に真面目に出席し、きちんと板書したことによって、指数がチャージされる。この逆を行った学生は、もちろん相当数がディスチャージされる(これがサステナジーかどうかにおいては、議論の余地があるが、少なくとも学生は何らかの手段を用いて指数を稼がなければならない)(これは、あくまで個人の主観で決定される要素なので、各人が、“何をもって豊かであるか”をIDにあらかじめ入力しておく必要性がある)。
なお、この制度を適用していく段階に応じて、貨幣の流通量を段階的に減らしていき、キャッシュ(現金)を用いて財の交換を行うのではなく、サステナジー指数および豊かさ指数を用いて財を購入する、といった概念を国民の間で浸透させていく。最終的に、現金で財を購入する際は、多額の手数料を徴収するようにして、現金の流通を国内において事実上禁止する(諸外国との為替相場では円は維持)。
⇒有史以来続いてきた貨幣経済からの脱却および真の人間主義に基づく民主主義社会の構築が狙い(資本主義からの脱却という意味ではなく、貨幣に代わる、新たな為替の概念の導入)。
(具体的な内容は第4部で述べる)
≪第3部のまとめ≫
『システムのために人間が働く』のではなく『人間のために、システムを働かせる』体制を構築する必要性がある。
もったいない総合研究会の経済の位置づけ(第3部)
『サステナジー社会』を実現するための経済性評価方法として、“行為・概念の数値化”という手法を導入する。
“行為・概念の数値化”
とは?
・日本国憲法第14条に抵触するであろう、『思想・表現の自由』を評価することである。サステナジー社会を目指すことを第一義とする。
⇒さまざまな物議を醸し出すであろう、危険な手法。
このリスクを低減するために、日本は一体、何を目指すのか?というテーゼの下、改憲を実現する必要性がある。
⇒あまりにも無謀である。
◆“行為・概念の数値化”の導入の前に、『サステナジー推進法』の名のもとに、国民全体に『国民証』(すべての国民サービスを享受するための電子モバイルID)を配布する。
国内において存在・流通しているすべての様々な財(動産・不動産問わず)に対して『サステナジー指数』と呼ばれる数値を適用し、その財に対して、-100~100のランク付け作業を国民総出で行う(国勢調査の要領)。
この結果算出されたサステナジー指数を国民一人一人が把握し、これにいくつかのランク幅を設け、そのカテゴリーにおいて、様々な優遇措置、あるいは罰則が科せられる制度を設ける。
(例)トップランナー方式の最新家電を購入すれば、サステナジー指数が100近くチャージされ、購入の際に、消費税等が免除される。逆に中古で電気効率の悪い旧式の製品を購入すれば、サステナジー指数は逆に30程度ディスチャージされ、それに伴い、高利率の炭素税が課せられる。
このように、国内のすべての財に対し、サステナジー指数を適用し、国民が『サステナジー社会』を実現したくなるような購買意欲を掻き立てる政策を様々な分野に渡って施行する。
・また、企業の評価指数としての利用価値も十分に見込めるので、積極的に導入していくべきである。
・このサステナジー指数が十分に浸透したら、“サービスのサステナジー化”を推進していく。
ここで注意すべきは、サービスにおけるサステナジー化は“低炭素”ではなく、各人における『満足度=快適度=充足度』等を評価し、これを“豊かさ指数”(-100~100++)に変換し、これの総量でそのサービスを正しく評価する。これもサステナジー指数同様、これにいくつかのランク幅を設け、そのカテゴリーにおいて、様々な優遇措置、あるいは罰則が科せられる制度を設ける。これは、先述した通り、サステナジーな社会に即した業務活動、社会活動または知的生産活動等を、評価の最上位として位置づけ、国民の社会的身分に関わらず、一律に評価するものである。よって、このような活動を行うことが、各人にとって、直接的な“収入”となる。
(例)ある学生が、授業を受ける為に講義室に入る際IDを翳し、(IDに接続された電子化された)ノートにきちんと板書し、退室する際にIDを再び翳すことによって、その授業に真面目に出席し、きちんと板書したことによって、指数がチャージされる。この逆を行った学生は、もちろん相当数がディスチャージされる(これがサステナジーかどうかにおいては、議論の余地があるが、少なくとも学生は何らかの手段を用いて指数を稼がなければならない)(これは、あくまで個人の主観で決定される要素なので、各人が、“何をもって豊かであるか”をIDにあらかじめ入力しておく必要性がある)。
なお、この制度を適用していく段階に応じて、貨幣の流通量を段階的に減らしていき、キャッシュ(現金)を用いて財の交換を行うのではなく、サステナジー指数および豊かさ指数を用いて財を購入する、といった概念を国民の間で浸透させていく。最終的に、現金で財を購入する際は、多額の手数料を徴収するようにして、現金の流通を国内において事実上禁止する(諸外国との為替相場では円は維持)。
⇒有史以来続いてきた貨幣経済からの脱却および真の人間主義に基づく民主主義社会の構築が狙い(資本主義からの脱却という意味ではなく、貨幣に代わる、新たな為替の概念の導入)。
(具体的な内容は第4部で述べる)
≪第3部のまとめ≫
『システムのために人間が働く』のではなく『人間のために、システムを働かせる』体制を構築する必要性がある。
PR
- +TRACKBACK URL+




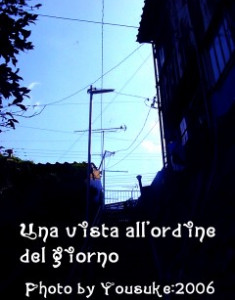
 :
: :0
:0 :
: 

