 :2025:05/17/22:02 ++ [PR]
:2025:05/17/22:02 ++ [PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
 :2009:05/28/14:12 ++ 地球温暖化懐疑論に対するコメント
:2009:05/28/14:12 ++ 地球温暖化懐疑論に対するコメント
地球温暖化論に対する非常に具体的な資料です。
ぜひ、ご覧ください。
http://www.cir.tohoku.ac.jp/~asuka/%E5%9C%B0%E7%90%83%E6%B8%A9%E6%9A%96%E5%8C%96%E5%95%8F%E9%A1%8C%E6%87%90%E7%96%91%E8%AB%96%E5%8F%8D%E8%AB%96%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88ver.24.pdf
ぜひ、ご覧ください。
http://www.cir.tohoku.ac.jp/~asuka/%E5%9C%B0%E7%90%83%E6%B8%A9%E6%9A%96%E5%8C%96%E5%95%8F%E9%A1%8C%E6%87%90%E7%96%91%E8%AB%96%E5%8F%8D%E8%AB%96%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88ver.24.pdf
PR
 :2009:05/28/01:08 ++ 過去の掲示板の抜粋
:2009:05/28/01:08 ++ 過去の掲示板の抜粋
掲示板に埋もれてしまうともったいないので、ここにいくつか挙げさせていただきます。
・・・・・・
“35歳”を救え
あすの日本 未来からの提言
http://www.nhk.or.jp/special/onair/090506.html
それは、
20年後の2029年には、
消費税が18%、
年金削減率28%と、
日本の最悪の経済状態を想定し、それに対して打てる対策は何かを考える番組でした。
その最悪の経済状態とは、これからGDPが横這いのゼロ成長で、正規雇用者が増加すると仮定した計算結果です。
NHKの提案した対策としては
①若い世代に対する積極的雇用政策
②安心して子育てのできる環境づくり
③家事と仕事を両立できる環境づくり
といったものでした。
ポイントとなるのは、
「モノへの投資から人への投資へ」
という、何度も言われていたフレーズです。
日本式の、土建業界への投資によってお金を循環させるスタイルでは行き詰まりを見せてきました。
この番組では、35歳の世代に焦点をあてて1万人アンケートをしていましたが、今の35歳が抱える問題は、
・収入が下がる
・安定した仕事を得られない
・収入が低いから子育てできない、子供を増やせない
→出生率0.86%(35歳の女性)
・将来に希望をもてない
とさまざまありました。
この問題を対処するために、「人への投資」です。
・職業訓練を政府が補助
・地方自治体が、子育て支援
・企業が、女性に対する福利厚生の充実
が例にあげられていました。
イギリスやフランスなど、ヨーロッパ諸国では対策が進んでいるようです。
フランスは徹底した子育て支援によって、10年間で出生率を1.68%から2.02%まであげたとか。
「人への投資」
これは、予算の問題と、国民の理解が必要であるようです。
確かに、今までの感覚では、本当によくなっていくのか疑ってしまうでしょう。
しかし、
「失業者を減らし、子供を増やし、活気を与えること」
これが日本の国力にとって重要であるようです。
実際に、三菱総合研究所の計算では、以上の対策によって20年後のGDPは政府計算のビジョンよりも良い結果になったようです。
私も、この提案に大いに賛成です。
「モノから人へ」
これが21世紀のキーワードになりそうです。
そこで、さらに深い考察ですが、
「今、日本が危ない」「収入がなく生活が苦しい」
といっても、世界にもっと貧しい人はたくさんいるわけで、それでも今後GDPを増やし続けることは、結果的に「貧しい人々を貧しいままにさせることにつながる」と思います。
正確には、上記の表現は、
「今までの生活水準に見合った欲求を満たすことができないのが苦しい」
というもので、問題は簡単ではありません。
自分でも、今の生活ができなくなるのは嫌です。
しかし、われらが掲げる「もったいない」の精神は、そこを追及していかなければいけないのではないでしょうか
・・・・・・・・
・・・・・・
“35歳”を救え
あすの日本 未来からの提言
http://www.nhk.or.jp/special/onair/090506.html
それは、
20年後の2029年には、
消費税が18%、
年金削減率28%と、
日本の最悪の経済状態を想定し、それに対して打てる対策は何かを考える番組でした。
その最悪の経済状態とは、これからGDPが横這いのゼロ成長で、正規雇用者が増加すると仮定した計算結果です。
NHKの提案した対策としては
①若い世代に対する積極的雇用政策
②安心して子育てのできる環境づくり
③家事と仕事を両立できる環境づくり
といったものでした。
ポイントとなるのは、
「モノへの投資から人への投資へ」
という、何度も言われていたフレーズです。
日本式の、土建業界への投資によってお金を循環させるスタイルでは行き詰まりを見せてきました。
この番組では、35歳の世代に焦点をあてて1万人アンケートをしていましたが、今の35歳が抱える問題は、
・収入が下がる
・安定した仕事を得られない
・収入が低いから子育てできない、子供を増やせない
→出生率0.86%(35歳の女性)
・将来に希望をもてない
とさまざまありました。
この問題を対処するために、「人への投資」です。
・職業訓練を政府が補助
・地方自治体が、子育て支援
・企業が、女性に対する福利厚生の充実
が例にあげられていました。
イギリスやフランスなど、ヨーロッパ諸国では対策が進んでいるようです。
フランスは徹底した子育て支援によって、10年間で出生率を1.68%から2.02%まであげたとか。
「人への投資」
これは、予算の問題と、国民の理解が必要であるようです。
確かに、今までの感覚では、本当によくなっていくのか疑ってしまうでしょう。
しかし、
「失業者を減らし、子供を増やし、活気を与えること」
これが日本の国力にとって重要であるようです。
実際に、三菱総合研究所の計算では、以上の対策によって20年後のGDPは政府計算のビジョンよりも良い結果になったようです。
私も、この提案に大いに賛成です。
「モノから人へ」
これが21世紀のキーワードになりそうです。
そこで、さらに深い考察ですが、
「今、日本が危ない」「収入がなく生活が苦しい」
といっても、世界にもっと貧しい人はたくさんいるわけで、それでも今後GDPを増やし続けることは、結果的に「貧しい人々を貧しいままにさせることにつながる」と思います。
正確には、上記の表現は、
「今までの生活水準に見合った欲求を満たすことができないのが苦しい」
というもので、問題は簡単ではありません。
自分でも、今の生活ができなくなるのは嫌です。
しかし、われらが掲げる「もったいない」の精神は、そこを追及していかなければいけないのではないでしょうか
・・・・・・・・
 :2009:05/26/19:44 ++ 総括班テレビ会議
:2009:05/26/19:44 ++ 総括班テレビ会議
昨日25日22:30~24:00において、総括班最終テレビ会議が行われ、発表内容およびリハーサルはほぼ完了したことをご報告します。
久保
久保
 :2009:05/14/11:03 ++ 二酸化炭素Part3
:2009:05/14/11:03 ++ 二酸化炭素Part3
もったいない総合研究会の経済の位置づけ(第3部)
『サステナジー社会』を実現するための経済性評価方法として、“行為・概念の数値化”という手法を導入する。
“行為・概念の数値化”
とは?
・日本国憲法第14条に抵触するであろう、『思想・表現の自由』を評価することである。サステナジー社会を目指すことを第一義とする。
⇒さまざまな物議を醸し出すであろう、危険な手法。
このリスクを低減するために、日本は一体、何を目指すのか?というテーゼの下、改憲を実現する必要性がある。
⇒あまりにも無謀である。
◆“行為・概念の数値化”の導入の前に、『サステナジー推進法』の名のもとに、国民全体に『国民証』(すべての国民サービスを享受するための電子モバイルID)を配布する。
国内において存在・流通しているすべての様々な財(動産・不動産問わず)に対して『サステナジー指数』と呼ばれる数値を適用し、その財に対して、-100~100のランク付け作業を国民総出で行う(国勢調査の要領)。
この結果算出されたサステナジー指数を国民一人一人が把握し、これにいくつかのランク幅を設け、そのカテゴリーにおいて、様々な優遇措置、あるいは罰則が科せられる制度を設ける。
(例)トップランナー方式の最新家電を購入すれば、サステナジー指数が100近くチャージされ、購入の際に、消費税等が免除される。逆に中古で電気効率の悪い旧式の製品を購入すれば、サステナジー指数は逆に30程度ディスチャージされ、それに伴い、高利率の炭素税が課せられる。
このように、国内のすべての財に対し、サステナジー指数を適用し、国民が『サステナジー社会』を実現したくなるような購買意欲を掻き立てる政策を様々な分野に渡って施行する。
・また、企業の評価指数としての利用価値も十分に見込めるので、積極的に導入していくべきである。
・このサステナジー指数が十分に浸透したら、“サービスのサステナジー化”を推進していく。
ここで注意すべきは、サービスにおけるサステナジー化は“低炭素”ではなく、各人における『満足度=快適度=充足度』等を評価し、これを“豊かさ指数”(-100~100++)に変換し、これの総量でそのサービスを正しく評価する。これもサステナジー指数同様、これにいくつかのランク幅を設け、そのカテゴリーにおいて、様々な優遇措置、あるいは罰則が科せられる制度を設ける。これは、先述した通り、サステナジーな社会に即した業務活動、社会活動または知的生産活動等を、評価の最上位として位置づけ、国民の社会的身分に関わらず、一律に評価するものである。よって、このような活動を行うことが、各人にとって、直接的な“収入”となる。
(例)ある学生が、授業を受ける為に講義室に入る際IDを翳し、(IDに接続された電子化された)ノートにきちんと板書し、退室する際にIDを再び翳すことによって、その授業に真面目に出席し、きちんと板書したことによって、指数がチャージされる。この逆を行った学生は、もちろん相当数がディスチャージされる(これがサステナジーかどうかにおいては、議論の余地があるが、少なくとも学生は何らかの手段を用いて指数を稼がなければならない)(これは、あくまで個人の主観で決定される要素なので、各人が、“何をもって豊かであるか”をIDにあらかじめ入力しておく必要性がある)。
なお、この制度を適用していく段階に応じて、貨幣の流通量を段階的に減らしていき、キャッシュ(現金)を用いて財の交換を行うのではなく、サステナジー指数および豊かさ指数を用いて財を購入する、といった概念を国民の間で浸透させていく。最終的に、現金で財を購入する際は、多額の手数料を徴収するようにして、現金の流通を国内において事実上禁止する(諸外国との為替相場では円は維持)。
⇒有史以来続いてきた貨幣経済からの脱却および真の人間主義に基づく民主主義社会の構築が狙い(資本主義からの脱却という意味ではなく、貨幣に代わる、新たな為替の概念の導入)。
(具体的な内容は第4部で述べる)
≪第3部のまとめ≫
『システムのために人間が働く』のではなく『人間のために、システムを働かせる』体制を構築する必要性がある。
もったいない総合研究会の経済の位置づけ(第3部)
『サステナジー社会』を実現するための経済性評価方法として、“行為・概念の数値化”という手法を導入する。
“行為・概念の数値化”
とは?
・日本国憲法第14条に抵触するであろう、『思想・表現の自由』を評価することである。サステナジー社会を目指すことを第一義とする。
⇒さまざまな物議を醸し出すであろう、危険な手法。
このリスクを低減するために、日本は一体、何を目指すのか?というテーゼの下、改憲を実現する必要性がある。
⇒あまりにも無謀である。
◆“行為・概念の数値化”の導入の前に、『サステナジー推進法』の名のもとに、国民全体に『国民証』(すべての国民サービスを享受するための電子モバイルID)を配布する。
国内において存在・流通しているすべての様々な財(動産・不動産問わず)に対して『サステナジー指数』と呼ばれる数値を適用し、その財に対して、-100~100のランク付け作業を国民総出で行う(国勢調査の要領)。
この結果算出されたサステナジー指数を国民一人一人が把握し、これにいくつかのランク幅を設け、そのカテゴリーにおいて、様々な優遇措置、あるいは罰則が科せられる制度を設ける。
(例)トップランナー方式の最新家電を購入すれば、サステナジー指数が100近くチャージされ、購入の際に、消費税等が免除される。逆に中古で電気効率の悪い旧式の製品を購入すれば、サステナジー指数は逆に30程度ディスチャージされ、それに伴い、高利率の炭素税が課せられる。
このように、国内のすべての財に対し、サステナジー指数を適用し、国民が『サステナジー社会』を実現したくなるような購買意欲を掻き立てる政策を様々な分野に渡って施行する。
・また、企業の評価指数としての利用価値も十分に見込めるので、積極的に導入していくべきである。
・このサステナジー指数が十分に浸透したら、“サービスのサステナジー化”を推進していく。
ここで注意すべきは、サービスにおけるサステナジー化は“低炭素”ではなく、各人における『満足度=快適度=充足度』等を評価し、これを“豊かさ指数”(-100~100++)に変換し、これの総量でそのサービスを正しく評価する。これもサステナジー指数同様、これにいくつかのランク幅を設け、そのカテゴリーにおいて、様々な優遇措置、あるいは罰則が科せられる制度を設ける。これは、先述した通り、サステナジーな社会に即した業務活動、社会活動または知的生産活動等を、評価の最上位として位置づけ、国民の社会的身分に関わらず、一律に評価するものである。よって、このような活動を行うことが、各人にとって、直接的な“収入”となる。
(例)ある学生が、授業を受ける為に講義室に入る際IDを翳し、(IDに接続された電子化された)ノートにきちんと板書し、退室する際にIDを再び翳すことによって、その授業に真面目に出席し、きちんと板書したことによって、指数がチャージされる。この逆を行った学生は、もちろん相当数がディスチャージされる(これがサステナジーかどうかにおいては、議論の余地があるが、少なくとも学生は何らかの手段を用いて指数を稼がなければならない)(これは、あくまで個人の主観で決定される要素なので、各人が、“何をもって豊かであるか”をIDにあらかじめ入力しておく必要性がある)。
なお、この制度を適用していく段階に応じて、貨幣の流通量を段階的に減らしていき、キャッシュ(現金)を用いて財の交換を行うのではなく、サステナジー指数および豊かさ指数を用いて財を購入する、といった概念を国民の間で浸透させていく。最終的に、現金で財を購入する際は、多額の手数料を徴収するようにして、現金の流通を国内において事実上禁止する(諸外国との為替相場では円は維持)。
⇒有史以来続いてきた貨幣経済からの脱却および真の人間主義に基づく民主主義社会の構築が狙い(資本主義からの脱却という意味ではなく、貨幣に代わる、新たな為替の概念の導入)。
(具体的な内容は第4部で述べる)
≪第3部のまとめ≫
『システムのために人間が働く』のではなく『人間のために、システムを働かせる』体制を構築する必要性がある。
『サステナジー社会』を実現するための経済性評価方法として、“行為・概念の数値化”という手法を導入する。
“行為・概念の数値化”
とは?
・日本国憲法第14条に抵触するであろう、『思想・表現の自由』を評価することである。サステナジー社会を目指すことを第一義とする。
⇒さまざまな物議を醸し出すであろう、危険な手法。
このリスクを低減するために、日本は一体、何を目指すのか?というテーゼの下、改憲を実現する必要性がある。
⇒あまりにも無謀である。
◆“行為・概念の数値化”の導入の前に、『サステナジー推進法』の名のもとに、国民全体に『国民証』(すべての国民サービスを享受するための電子モバイルID)を配布する。
国内において存在・流通しているすべての様々な財(動産・不動産問わず)に対して『サステナジー指数』と呼ばれる数値を適用し、その財に対して、-100~100のランク付け作業を国民総出で行う(国勢調査の要領)。
この結果算出されたサステナジー指数を国民一人一人が把握し、これにいくつかのランク幅を設け、そのカテゴリーにおいて、様々な優遇措置、あるいは罰則が科せられる制度を設ける。
(例)トップランナー方式の最新家電を購入すれば、サステナジー指数が100近くチャージされ、購入の際に、消費税等が免除される。逆に中古で電気効率の悪い旧式の製品を購入すれば、サステナジー指数は逆に30程度ディスチャージされ、それに伴い、高利率の炭素税が課せられる。
このように、国内のすべての財に対し、サステナジー指数を適用し、国民が『サステナジー社会』を実現したくなるような購買意欲を掻き立てる政策を様々な分野に渡って施行する。
・また、企業の評価指数としての利用価値も十分に見込めるので、積極的に導入していくべきである。
・このサステナジー指数が十分に浸透したら、“サービスのサステナジー化”を推進していく。
ここで注意すべきは、サービスにおけるサステナジー化は“低炭素”ではなく、各人における『満足度=快適度=充足度』等を評価し、これを“豊かさ指数”(-100~100++)に変換し、これの総量でそのサービスを正しく評価する。これもサステナジー指数同様、これにいくつかのランク幅を設け、そのカテゴリーにおいて、様々な優遇措置、あるいは罰則が科せられる制度を設ける。これは、先述した通り、サステナジーな社会に即した業務活動、社会活動または知的生産活動等を、評価の最上位として位置づけ、国民の社会的身分に関わらず、一律に評価するものである。よって、このような活動を行うことが、各人にとって、直接的な“収入”となる。
(例)ある学生が、授業を受ける為に講義室に入る際IDを翳し、(IDに接続された電子化された)ノートにきちんと板書し、退室する際にIDを再び翳すことによって、その授業に真面目に出席し、きちんと板書したことによって、指数がチャージされる。この逆を行った学生は、もちろん相当数がディスチャージされる(これがサステナジーかどうかにおいては、議論の余地があるが、少なくとも学生は何らかの手段を用いて指数を稼がなければならない)(これは、あくまで個人の主観で決定される要素なので、各人が、“何をもって豊かであるか”をIDにあらかじめ入力しておく必要性がある)。
なお、この制度を適用していく段階に応じて、貨幣の流通量を段階的に減らしていき、キャッシュ(現金)を用いて財の交換を行うのではなく、サステナジー指数および豊かさ指数を用いて財を購入する、といった概念を国民の間で浸透させていく。最終的に、現金で財を購入する際は、多額の手数料を徴収するようにして、現金の流通を国内において事実上禁止する(諸外国との為替相場では円は維持)。
⇒有史以来続いてきた貨幣経済からの脱却および真の人間主義に基づく民主主義社会の構築が狙い(資本主義からの脱却という意味ではなく、貨幣に代わる、新たな為替の概念の導入)。
(具体的な内容は第4部で述べる)
≪第3部のまとめ≫
『システムのために人間が働く』のではなく『人間のために、システムを働かせる』体制を構築する必要性がある。
もったいない総合研究会の経済の位置づけ(第3部)
『サステナジー社会』を実現するための経済性評価方法として、“行為・概念の数値化”という手法を導入する。
“行為・概念の数値化”
とは?
・日本国憲法第14条に抵触するであろう、『思想・表現の自由』を評価することである。サステナジー社会を目指すことを第一義とする。
⇒さまざまな物議を醸し出すであろう、危険な手法。
このリスクを低減するために、日本は一体、何を目指すのか?というテーゼの下、改憲を実現する必要性がある。
⇒あまりにも無謀である。
◆“行為・概念の数値化”の導入の前に、『サステナジー推進法』の名のもとに、国民全体に『国民証』(すべての国民サービスを享受するための電子モバイルID)を配布する。
国内において存在・流通しているすべての様々な財(動産・不動産問わず)に対して『サステナジー指数』と呼ばれる数値を適用し、その財に対して、-100~100のランク付け作業を国民総出で行う(国勢調査の要領)。
この結果算出されたサステナジー指数を国民一人一人が把握し、これにいくつかのランク幅を設け、そのカテゴリーにおいて、様々な優遇措置、あるいは罰則が科せられる制度を設ける。
(例)トップランナー方式の最新家電を購入すれば、サステナジー指数が100近くチャージされ、購入の際に、消費税等が免除される。逆に中古で電気効率の悪い旧式の製品を購入すれば、サステナジー指数は逆に30程度ディスチャージされ、それに伴い、高利率の炭素税が課せられる。
このように、国内のすべての財に対し、サステナジー指数を適用し、国民が『サステナジー社会』を実現したくなるような購買意欲を掻き立てる政策を様々な分野に渡って施行する。
・また、企業の評価指数としての利用価値も十分に見込めるので、積極的に導入していくべきである。
・このサステナジー指数が十分に浸透したら、“サービスのサステナジー化”を推進していく。
ここで注意すべきは、サービスにおけるサステナジー化は“低炭素”ではなく、各人における『満足度=快適度=充足度』等を評価し、これを“豊かさ指数”(-100~100++)に変換し、これの総量でそのサービスを正しく評価する。これもサステナジー指数同様、これにいくつかのランク幅を設け、そのカテゴリーにおいて、様々な優遇措置、あるいは罰則が科せられる制度を設ける。これは、先述した通り、サステナジーな社会に即した業務活動、社会活動または知的生産活動等を、評価の最上位として位置づけ、国民の社会的身分に関わらず、一律に評価するものである。よって、このような活動を行うことが、各人にとって、直接的な“収入”となる。
(例)ある学生が、授業を受ける為に講義室に入る際IDを翳し、(IDに接続された電子化された)ノートにきちんと板書し、退室する際にIDを再び翳すことによって、その授業に真面目に出席し、きちんと板書したことによって、指数がチャージされる。この逆を行った学生は、もちろん相当数がディスチャージされる(これがサステナジーかどうかにおいては、議論の余地があるが、少なくとも学生は何らかの手段を用いて指数を稼がなければならない)(これは、あくまで個人の主観で決定される要素なので、各人が、“何をもって豊かであるか”をIDにあらかじめ入力しておく必要性がある)。
なお、この制度を適用していく段階に応じて、貨幣の流通量を段階的に減らしていき、キャッシュ(現金)を用いて財の交換を行うのではなく、サステナジー指数および豊かさ指数を用いて財を購入する、といった概念を国民の間で浸透させていく。最終的に、現金で財を購入する際は、多額の手数料を徴収するようにして、現金の流通を国内において事実上禁止する(諸外国との為替相場では円は維持)。
⇒有史以来続いてきた貨幣経済からの脱却および真の人間主義に基づく民主主義社会の構築が狙い(資本主義からの脱却という意味ではなく、貨幣に代わる、新たな為替の概念の導入)。
(具体的な内容は第4部で述べる)
≪第3部のまとめ≫
『システムのために人間が働く』のではなく『人間のために、システムを働かせる』体制を構築する必要性がある。
 :2009:05/08/01:36 ++ 二酸化炭素part2
:2009:05/08/01:36 ++ 二酸化炭素part2
もったいない総合研究会の経済の位置づけ(第2部)
・人類が経済活動を行うと、二酸化炭素が排出されるのは自明の理
⇒これの回避は熱力学第二法則に反する。
(宇宙の進化はエントロピー増大側に則っているので、現状のテクノロジーでのこれの克服は不可能)
(*もったいない総合研究会で調査しているあるテクノロジーが実用化されれば別な展開もあるかも知れない)
・二酸化炭素の排出量を削減するには、どうすればよいのか?
◆“経済規模を縮小する”
⇒資本主義体制の崩壊を招きかねない。
(ただ、資本主義に代わる新たな体制が確立されれば、話は別である。また、金融による取引を必要としない経済システムが確立されても同じことが言える)
◆“(産業)人口を削減する“
⇒民主主義と相反する構想であり、最たる人権侵害であるが、日本をはじめ諸先進国では既に自然にこのような兆候が顕在化してきている。
(ある程度認識しなければならない真実である)
◆“新たなシステムを構築して、その中で二酸化炭素の取引をする”
⇒代表的なものに、京都メカニズムなどが挙げられる。
(これは、氷山の一角ともいうべき対象であって、昨年秋以来の金融恐慌以来、投資がすべて“低炭素”の方向に向かって流れているのは明らかである。大変喜ばしいことではあるが、この結末が世界に同様な結末をもたらすのかは、あまり議論されることはない。“低炭素”のみが果たしてサステナジーな社会を構築してくれるのか?我々はこのような懐疑的な一面も持ち合わせた上で、十分にこの結末を吟味していかなければならない。(例)バイオ燃料を作るために、世界の穀物価格バランスを崩す⇒世界的な食糧不足に陥る危険性)
⇒“炭素取引”は現に実用化されており、実際、我が国はこのメカニズムをもちいて2012を達成しようとしている。
(炭素が高額で取引されている最たる象徴)
・われわれが経済性(この場合豊かさ)を鑑みず、ひたすらに低炭素社会を実現するために邁進したとする(たとえば2050年までに世界全体でCO2半減)
⇒客観的に、われわれが不可抗力によって排出する二酸化炭素は森林吸収減等と等しくなり、理想的な炭素循環は実現すると思われる。
⇒しかしながら、われわれが経済市場原理を手放すということは、資本主義を放棄(または脱却)することであり、これすなわち、(現状の)民主主義体制の崩壊を意味する⇒第二の市民革命(産業革命)に匹敵するものでなければならない。
⇒(現状の不完全な体制では)最終的に炭素を通過機軸として、持たざる者(発展途上国)が持つ者(先進国)によって(市場、経済が)支配されるといった、帝国主義の再来たる懸念も生じてくる。
*最たる論点は、これからの世界統治体制は、どうあるべきか?
に帰着するのではないか?
実際の話、現在10億にも満たない我々が先進国が、かつて一方的に確立した経済原理を用いて資源欲しさに世界各地に武力を用いて進出し、大量の化石資源を消費し、経済を発展させ世界を支配した挙句、その弊害は70億に達そうとしている世界人類の頭上とその未来に平等に降り注いでいる。
これは、産業革命&市民革命以降の世界の歴史の要約である。
・かつて、イギリスのチャップリン首相が、
『民主主義は最悪の統治システムである。これまで存在してきたあらゆる統治体制を除いては。』
と述べたように、経済市場主義はたとえ欠陥があるにしても、民主主義社会を目指す以上、不可欠なシステムであることは間違いない。
しかしながら、昨年以来噴出し出した、このシステムの具体的な欠陥に、世界中が悲鳴を上げているのは事実である。
アメリカの第35代大統領J.F.ケネディはかつてこう述べた。
『世界で起こるあらゆる事象は、ある必然的な意志によって支配されている。』
・・・・『神の見えざる手』は、本当に『神』なのか?
■STEPにおいて、経済性を評価することは果たして可能なのか?
>>可能である。
■どうするのか?
>>もったいない総合研究会としては、“行為・概念の数値化”を検討している。
■どういうことか?
>>サステナジーな社会に即した社会活動または知的生産活動を、評価の最上位として位置づけ、この概念をもとに、経済システムを再構築する。
(詳細は第3部)
■実現見込みがあるのか?
>>現段階では、かなり少ない。しかしながら、かつてこのようなコミュニティーは世界中で多く存在していた。
(例)日本の江戸時代
■大まかな方向性
>>かつてこの国が200年間もの長きに渡って戦争がなく、完全に閉じたシステム(鎖国)の中で経済活動を全うしてきたという歴史と、和という調和を尊ぶ質実剛健な精神を思い返し、自然界に存在しているような、最小のエネルギーで駆動し、最も効率のよいシステムである生態系そのものが持つ食物連鎖、水循環、炭素循環等を参考とし、そのような自然の中で知恵とテクノロジーをはぐくみ、その中で共存する、といった経済システムを確立すること。
⇒近代の実績から、日本にしか成さない技ではないか?
全世界に先駆け、完全な『サステナジー社会』を実現するために、変革を起こしていく。
◆(現在の)低炭素革命の目的は、炭素に値段をつけて、経済の取引の材料にすることであり、本気で将来実現すべき『サステナジー社会』構築に向けて投資がなされているものではない。
⇒歴史は、埋蔵資源完全枯渇といった最終局面に直面した時に、繰り返す。
⇒この悪しき連鎖を断ち切らなければならない。
≪第二部のまとめ≫
『変えなければならないのは、弱者と強者を生み出す経済システムそのものであり、考えないといけないことは、これからの地球家族の共生の在り方である。』
・人類が経済活動を行うと、二酸化炭素が排出されるのは自明の理
⇒これの回避は熱力学第二法則に反する。
(宇宙の進化はエントロピー増大側に則っているので、現状のテクノロジーでのこれの克服は不可能)
(*もったいない総合研究会で調査しているあるテクノロジーが実用化されれば別な展開もあるかも知れない)
・二酸化炭素の排出量を削減するには、どうすればよいのか?
◆“経済規模を縮小する”
⇒資本主義体制の崩壊を招きかねない。
(ただ、資本主義に代わる新たな体制が確立されれば、話は別である。また、金融による取引を必要としない経済システムが確立されても同じことが言える)
◆“(産業)人口を削減する“
⇒民主主義と相反する構想であり、最たる人権侵害であるが、日本をはじめ諸先進国では既に自然にこのような兆候が顕在化してきている。
(ある程度認識しなければならない真実である)
◆“新たなシステムを構築して、その中で二酸化炭素の取引をする”
⇒代表的なものに、京都メカニズムなどが挙げられる。
(これは、氷山の一角ともいうべき対象であって、昨年秋以来の金融恐慌以来、投資がすべて“低炭素”の方向に向かって流れているのは明らかである。大変喜ばしいことではあるが、この結末が世界に同様な結末をもたらすのかは、あまり議論されることはない。“低炭素”のみが果たしてサステナジーな社会を構築してくれるのか?我々はこのような懐疑的な一面も持ち合わせた上で、十分にこの結末を吟味していかなければならない。(例)バイオ燃料を作るために、世界の穀物価格バランスを崩す⇒世界的な食糧不足に陥る危険性)
⇒“炭素取引”は現に実用化されており、実際、我が国はこのメカニズムをもちいて2012を達成しようとしている。
(炭素が高額で取引されている最たる象徴)
・われわれが経済性(この場合豊かさ)を鑑みず、ひたすらに低炭素社会を実現するために邁進したとする(たとえば2050年までに世界全体でCO2半減)
⇒客観的に、われわれが不可抗力によって排出する二酸化炭素は森林吸収減等と等しくなり、理想的な炭素循環は実現すると思われる。
⇒しかしながら、われわれが経済市場原理を手放すということは、資本主義を放棄(または脱却)することであり、これすなわち、(現状の)民主主義体制の崩壊を意味する⇒第二の市民革命(産業革命)に匹敵するものでなければならない。
⇒(現状の不完全な体制では)最終的に炭素を通過機軸として、持たざる者(発展途上国)が持つ者(先進国)によって(市場、経済が)支配されるといった、帝国主義の再来たる懸念も生じてくる。
*最たる論点は、これからの世界統治体制は、どうあるべきか?
に帰着するのではないか?
実際の話、現在10億にも満たない我々が先進国が、かつて一方的に確立した経済原理を用いて資源欲しさに世界各地に武力を用いて進出し、大量の化石資源を消費し、経済を発展させ世界を支配した挙句、その弊害は70億に達そうとしている世界人類の頭上とその未来に平等に降り注いでいる。
これは、産業革命&市民革命以降の世界の歴史の要約である。
・かつて、イギリスのチャップリン首相が、
『民主主義は最悪の統治システムである。これまで存在してきたあらゆる統治体制を除いては。』
と述べたように、経済市場主義はたとえ欠陥があるにしても、民主主義社会を目指す以上、不可欠なシステムであることは間違いない。
しかしながら、昨年以来噴出し出した、このシステムの具体的な欠陥に、世界中が悲鳴を上げているのは事実である。
アメリカの第35代大統領J.F.ケネディはかつてこう述べた。
『世界で起こるあらゆる事象は、ある必然的な意志によって支配されている。』
・・・・『神の見えざる手』は、本当に『神』なのか?
■STEPにおいて、経済性を評価することは果たして可能なのか?
>>可能である。
■どうするのか?
>>もったいない総合研究会としては、“行為・概念の数値化”を検討している。
■どういうことか?
>>サステナジーな社会に即した社会活動または知的生産活動を、評価の最上位として位置づけ、この概念をもとに、経済システムを再構築する。
(詳細は第3部)
■実現見込みがあるのか?
>>現段階では、かなり少ない。しかしながら、かつてこのようなコミュニティーは世界中で多く存在していた。
(例)日本の江戸時代
■大まかな方向性
>>かつてこの国が200年間もの長きに渡って戦争がなく、完全に閉じたシステム(鎖国)の中で経済活動を全うしてきたという歴史と、和という調和を尊ぶ質実剛健な精神を思い返し、自然界に存在しているような、最小のエネルギーで駆動し、最も効率のよいシステムである生態系そのものが持つ食物連鎖、水循環、炭素循環等を参考とし、そのような自然の中で知恵とテクノロジーをはぐくみ、その中で共存する、といった経済システムを確立すること。
⇒近代の実績から、日本にしか成さない技ではないか?
全世界に先駆け、完全な『サステナジー社会』を実現するために、変革を起こしていく。
◆(現在の)低炭素革命の目的は、炭素に値段をつけて、経済の取引の材料にすることであり、本気で将来実現すべき『サステナジー社会』構築に向けて投資がなされているものではない。
⇒歴史は、埋蔵資源完全枯渇といった最終局面に直面した時に、繰り返す。
⇒この悪しき連鎖を断ち切らなければならない。
≪第二部のまとめ≫
『変えなければならないのは、弱者と強者を生み出す経済システムそのものであり、考えないといけないことは、これからの地球家族の共生の在り方である。』




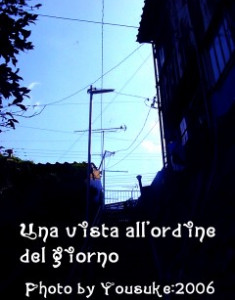
 :
: :0
:0 :
: 
